現場で「何度も同じことを説明して疲れる…」「教えるたびに内容が違っていて混乱する…」
そんな声を耳にすること、ありませんか?
私は教育委員として、入職者や異動してきたスタッフへの説明を繰り返す中で、こんな課題に直面しました。
- 教える人によって説明の内容にばらつきがある
- 聞く側も、毎回違うことを言われて混乱する
- 教える側も、毎回同じことを繰り返すストレスがある
これって、双方にとって非効率で、気持ちもすれ違いやすい状態だと思ったんです。
そこで、「一度教えた内容を、自分で振り返りながら実践できるようにしたい」という思いから、入院処理の手順を 電子カルテ上に文章化・見える化する仕組みを提案しました。
“調べてから聞く”仕組みを整えたかった
医療現場では、「何でも聞いていいよ」というスタンスも大切です。でも、その前に「まず調べてみる」「確認してみる」ことができると、自立した行動にもつながります。
この手順を見える化することで、
- 一度教えた内容をいつでも確認できる
- 教える側も都度の説明負担が軽減
- 内容の統一性が保たれる
- 変更があったときもすぐに修正できる
そんな好循環が生まれるのでは?と考えました。
“巻き込み力”で仕組みを作った
この手順のデジタル化は、私ひとりで作り上げたものではありません。
看護基準・手順委員のメンバーと協力し、役職者の方々にも確認していただきながら進めました。
そして最終的には、手順書の紙ファイルをすべて電子カルテ上に導入するという、大きな動きにもつながりました。
これにより、どのパソコンからでもすぐに手順を確認できる環境が整い、現場のスタッフが“必要な情報にすぐアクセスできる”ようになったのです。
見える化が、好循環のスパイラルを生んだ
「これがあるから助かる!」
「すぐに手順が確認できて安心です」
そんな声が、他部署のスタッフや病棟スタッフからも届いています。
私が日勤でいないときでも、誰かがこの手順を見て動いてくれている。
そんな風に、日勤か夜勤かに関係なく貢献できる仕組みになったことが、私にとっても大きな達成感でした。
まとめ:仕組みを整えることは、人を助けること
見える化とは、「誰かの頭の中の当たり前」を「みんなで共有できるカタチ」にすること。
この取り組みは、手順の電子化という業務改善だけでなく、
- 教育の統一
- 教える側の負担軽減
- スタッフの自立的行動の促進
- 他の委員会との連携の可能性
など、多くのプラスを生み出す 好循環の第一歩となりました。
教育委員としての視点から見える問題を、ちょっとした工夫で改善できるかもしれません。
あなたの現場でも、「見える化」を一つずつ進めてみませんか?
あとがき
あ、もしかしたら…
これが 共育デザイナーとしての力量が発揮された瞬間なのかもしれませんね(自画自賛😂)
ここまで読んでくださって、本当にありがとうございました。
あなたの病棟でも、なにかのヒントやきっかけになったらとても嬉しいです😊
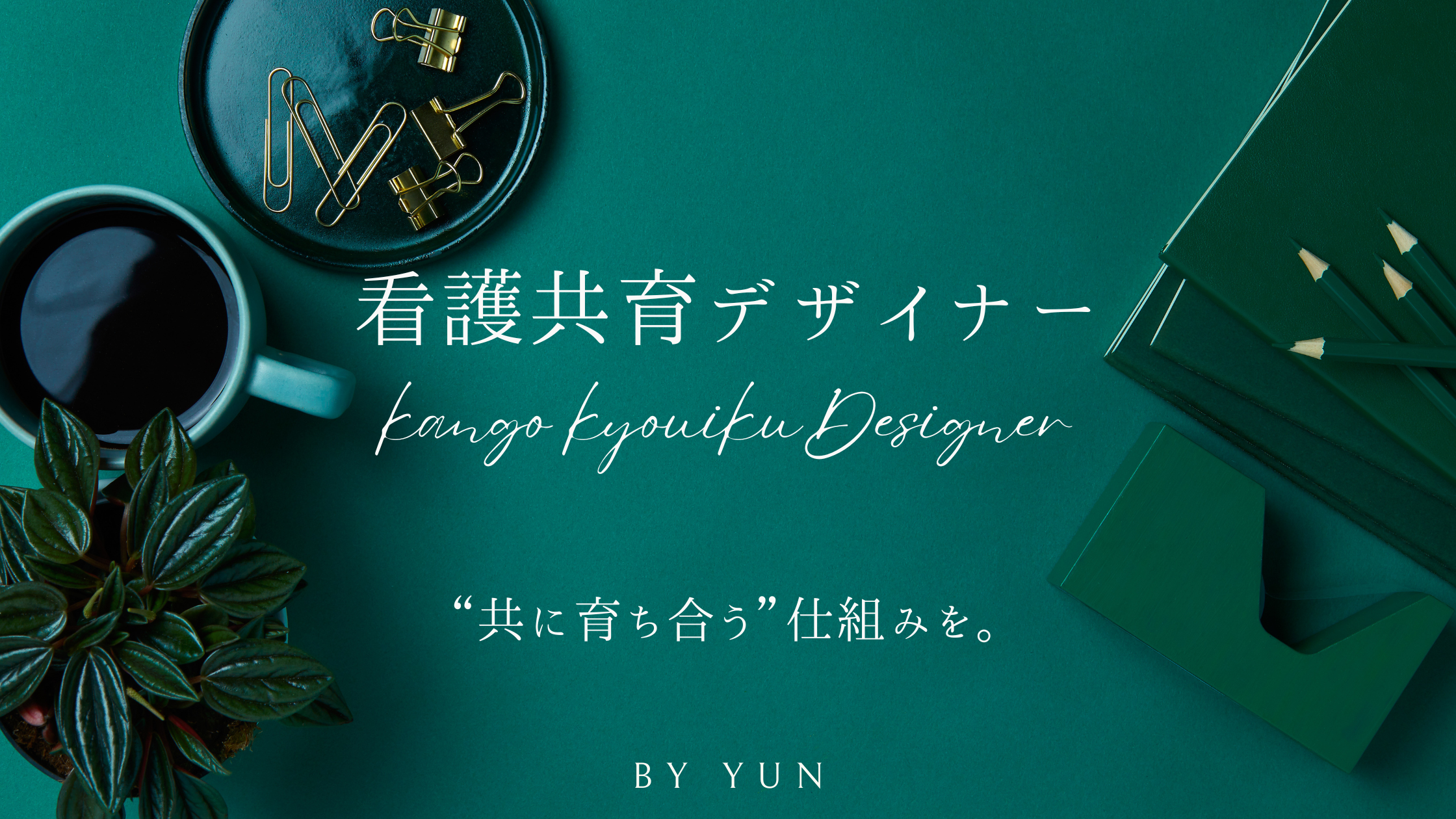
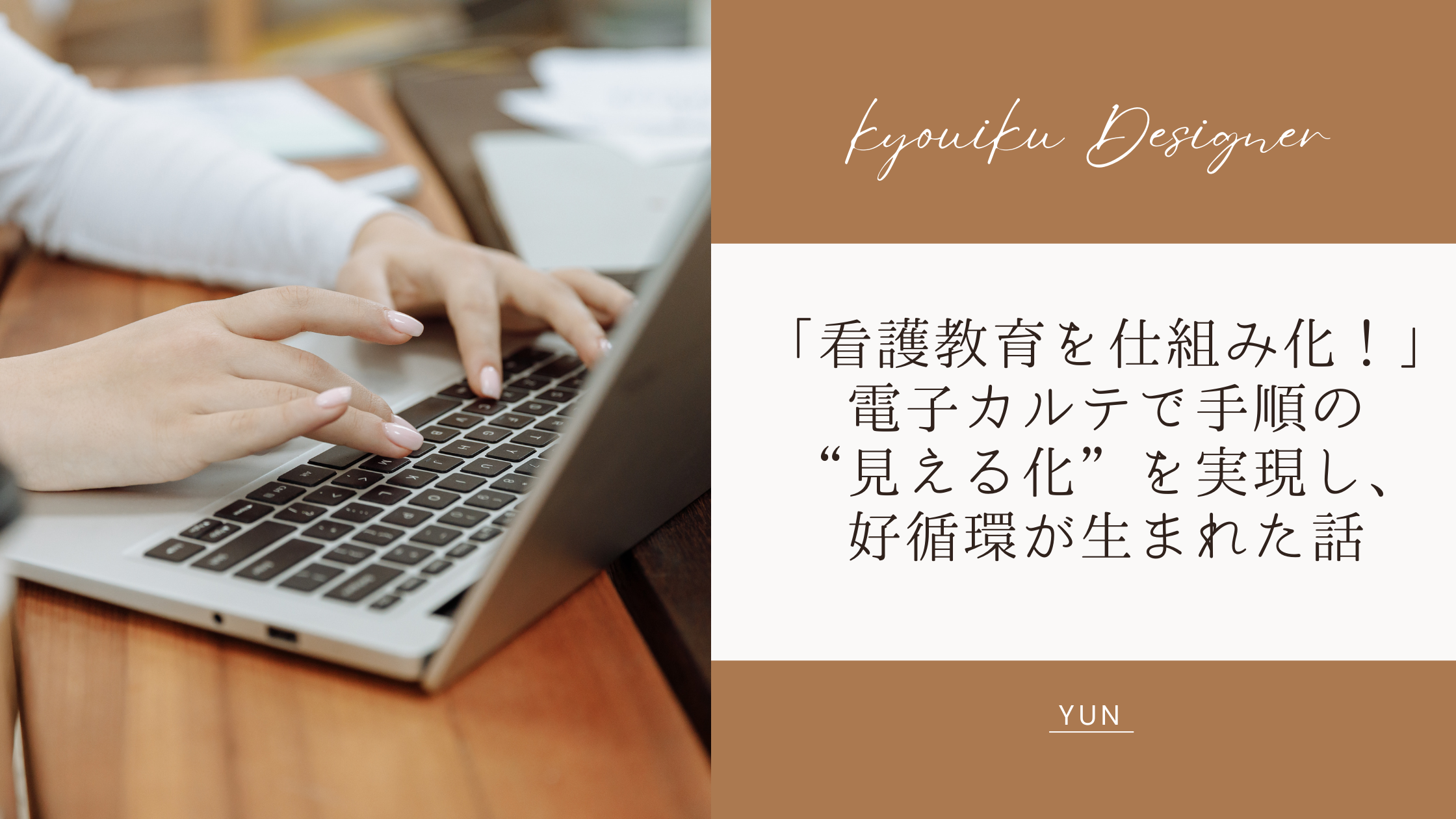

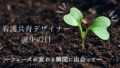
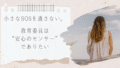
コメント