〜HSP気質を活かして病棟で力を発揮する方法〜
はじめに
看護の現場では、
患者さんの小さな変化やスタッフの雰囲気、家族の想いまで敏感に感じ取る力が求められます。
でもその力が強すぎると、「見えすぎて疲れる」こともありますよね。
私自身もそうです。
足音・物音・モニター音・人の表情…ぜんぶ拾ってしまうタイプで、
「気にしすぎなのかな」と思うこともあります。
でも最近は、この「見える力」は病棟で働く上での大きな武器になると感じています。
1. 見えすぎてしまうから疲れること
私は、意識しなくても周囲の雰囲気や人の感情を拾ってしまいます。
- 上のスタッフがイライラしているとすぐわかる
→ 急に無視されたり、ピリピリした空気を感じるとこちらも疲弊します。 - 部屋の割り振りやフォロー体制の不均衡が目に入る
→ 「この割り振りは過負荷すぎるな」「あのスタッフはフォロー不足で困ってるな」などが自然とわかります。 - 医師や患者家族の感情まで感じ取ってしまう
→ 家族の不安や医師の焦りを察してしまい、つい気を使いすぎることも。 - 他のスタッフの困りごとを見つけてしまう
→ 結果、助けようと動いてしまい、自分の業務負担が増えることもあります。
見たくなくても見えてしまうし、感じたくなくても感じてしまう。
これが、私のようなHSP気質を持つ看護師の「しんどさ」だと思います。
2. 見える力を活かせる場面
一方で、この「見える力」は教育やフォローの場面では圧倒的な武器になります。
- 新人や救急初対応スタッフの不安に、すぐ声をかけられる
- 患者さんの小さな異変や家族の不安を早くキャッチできる
- フォロー不足のスタッフに先回りでサポートができる
- 部屋割りや負荷の偏りに気づき、師長に相談して早めに調整できる
見えるからこそ、問題を早めに察知して動けるんです。
これは教育担当としても、現場のメンバーとしても大きな強みだと実感しています。
3. 見えすぎる人が疲れにくくなる工夫
ただ、この力を活かすためには「全部を抱え込まない」ことが大切です。
- 割り振りの問題 → 師長や他の役職者に委ねる
- フォロー不足スタッフ → 必要最低限のサポートだけ
- イライラしているスタッフ → 深く関わらず距離を取る
- 患者家族や医師の感情 → 必要な情報だけを受け取る
「見えるけど、すべては抱えない」
この意識を持つようになってから、少しずつ気持ちが楽になりました。
おわりに
見えすぎることは、決して弱点ではありません。
それは誰よりも早く変化に気づける力であり、
看護の現場では患者さんを守るための大きな強みになります。
ただ、その力をすべて受け止めようとすると疲れてしまうので、
「何を拾って、何を手放すか」を決めることが大事です。
見える力を活かしながら、無理なく働ける環境を作っていきたいなと思います。
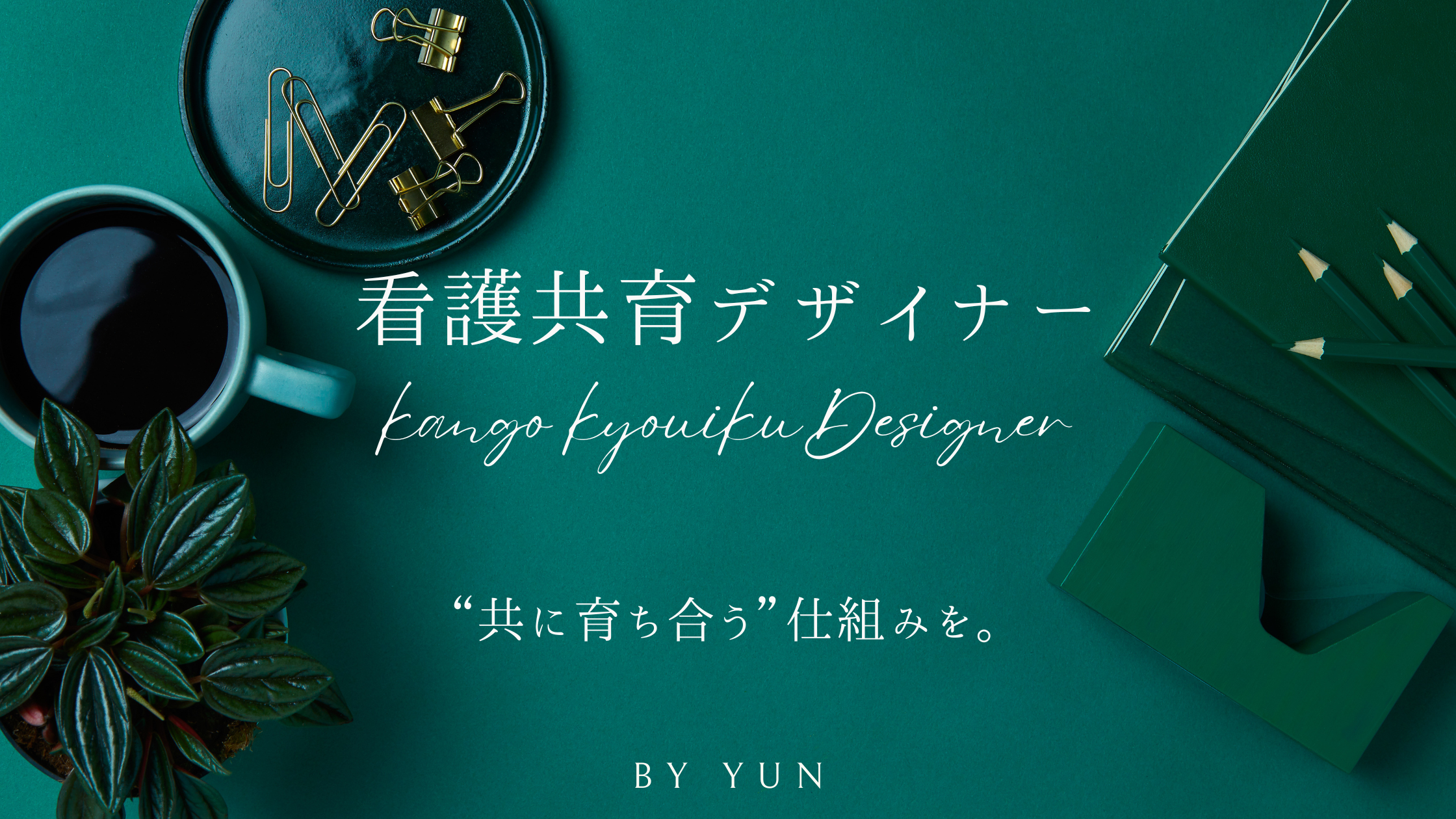
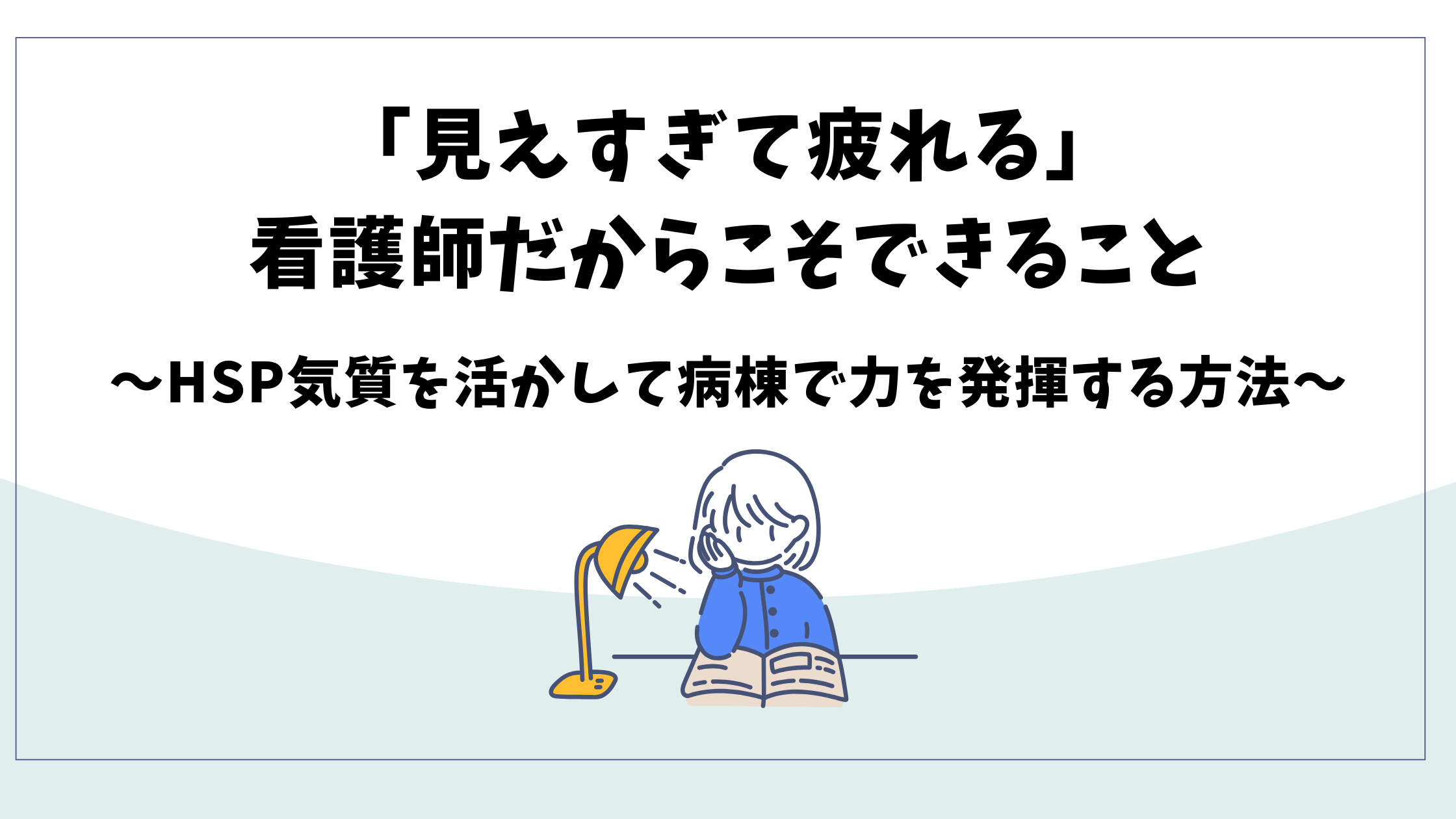

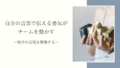
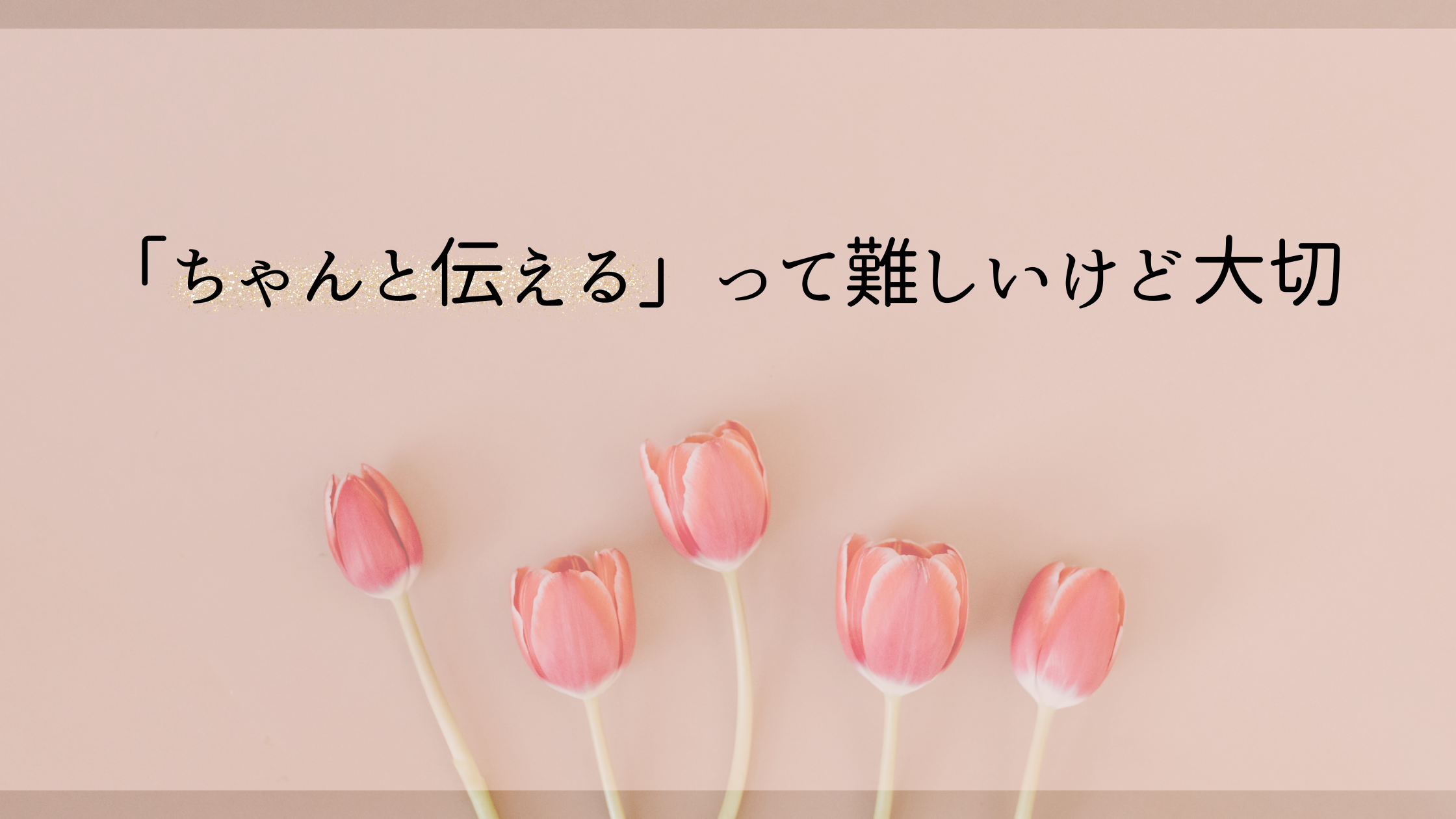
コメント