最近私が意識しているのが、フォローするスタッフの「頭の中を見に行く」感覚で関わること。
相手がどこまで理解していて、何がわかっていないのか。それを一緒に探っていくんです。
これが案外楽しくて、相手も自分の「分かっていないポイント」に気づけます。
実際のフォローでやってみたこと
先日、術後2日目の患者さんを受け持つ2年目のスタッフのフォローにつきました。
フォローの時にまず私がやったのは、
「この患者さん、手術前の状態どうだった?」と問いかけること。
すると、手術前の病態やバックグラウンドを説明してくれたんですが、情報が少し曖昧だったので、足りない部分を補いながら一緒に整理。
そこから、「どういう手術をしたの?」と聞いて、絵に描いてもらいました。
やっぱり絵にすることで、頭の中の整理が進むし、何となく理解していた部分が可視化される。
これは本当に効果的でした。
結局自分ではかけなかったので、受け持つ前にで画像を探して準備しておきました。
かけないときはイメージできるように視覚的にもアプローチする。
術後の身体変化を考えながらアセスメントする視点
さらに、術後の回復過程に合わせて一緒に患者さんの状態を照らし合わせてアセスメントを行いました。
「今、患者さんはどういう身体の状態にあるか」「何に注意すべきか」を整理しながら、一つひとつ確認。
相手からは、
🗣️「術後の身体変化を考えながらアセスメントする視点を学べたけど、自分が学習してきたことや見ている視点は大きく間違っていないな、とも思いました」
という言葉が聞けました。
自分は間違っていないんだ、と気づけたことも大きな収穫だったと思います。
自分の学習に自信を持ってほしいと思います。
ときには、忙殺される日々から少し解放してあげて、
家庭教師のように一対一でしっかりアセスメントしながら受け持つ時間を設けることが
大事だなと、教育委員として改めて感じた一日でした。
振り返りでの気づきと成長
フォロー終わりには、振り返りと次回の課題も一緒に確認します。
その子が特に課題としている忘れやすさの不安も言葉にされました。
🗣️「今日教えてもらったこと、忘れそうで心配です…」とも言っていたので、
「じゃあ、今日の振り返りをまとめてみて!一緒に検索した資料とかメモも活用して、自分なりに思い出せる形にしてまた見せて!」と伝えました。
次回見せてもらうのが楽しみです。
おわりに
教育って、知識を教えるだけじゃなくて、相手の頭の中を一緒に整理していくプロセスが本当に大事だなと改めて感じた1日でした。
相手のことを「分かってるつもり」が一番怖いから、そこをクリアにしてあげる関わりをこれからも大事にしたいなと思います。
✔️ この記事のメッセージ
- フォロー時は「頭の中を一緒に整理する」視点で関わる
- 見える化(絵や表)は理解度アップのカギ
- 学んだことを自分の言葉にする振り返りを大切にする
- 忙しい日々でも、あえて一対一でじっくり関わる時間が重要
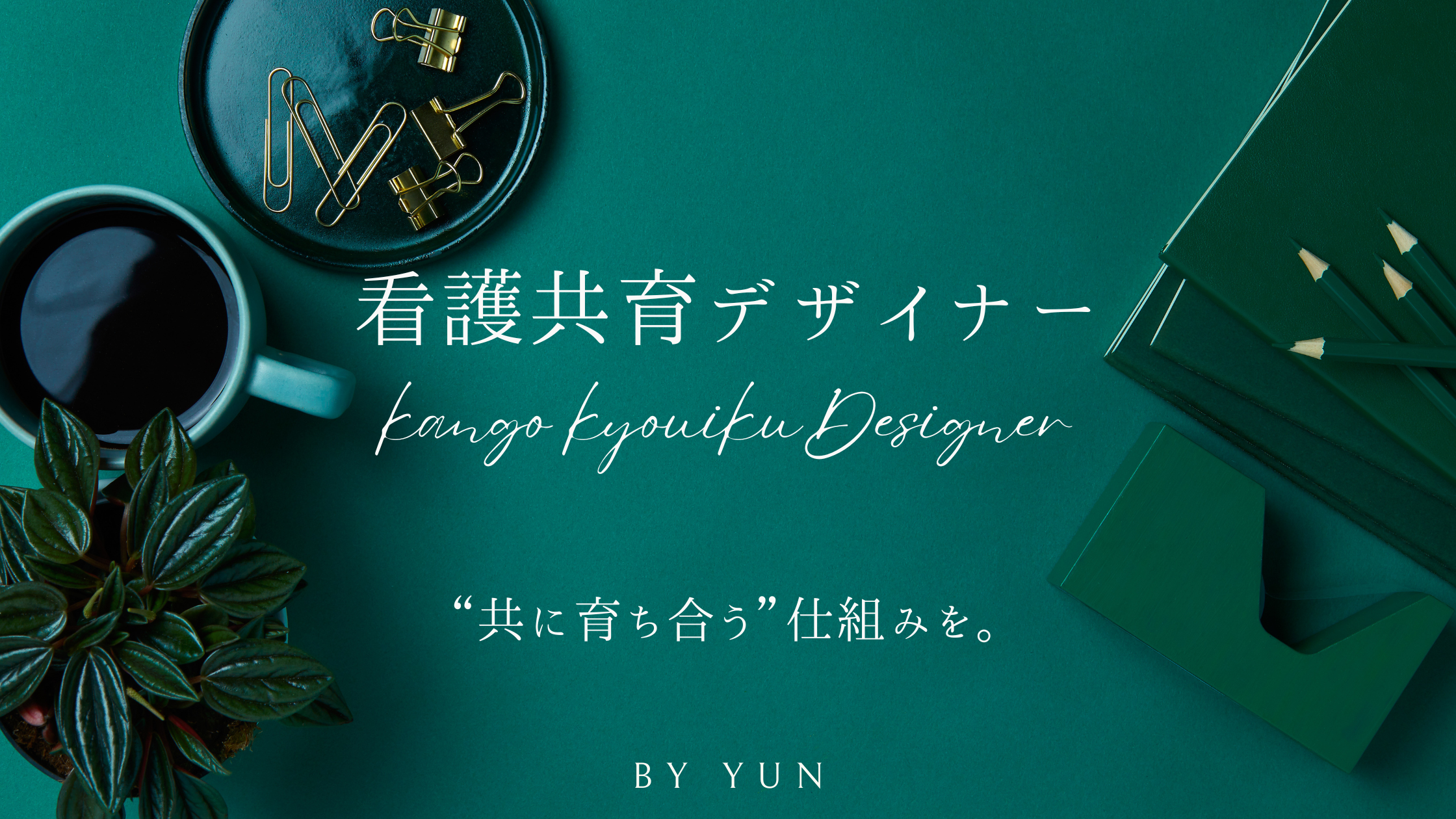
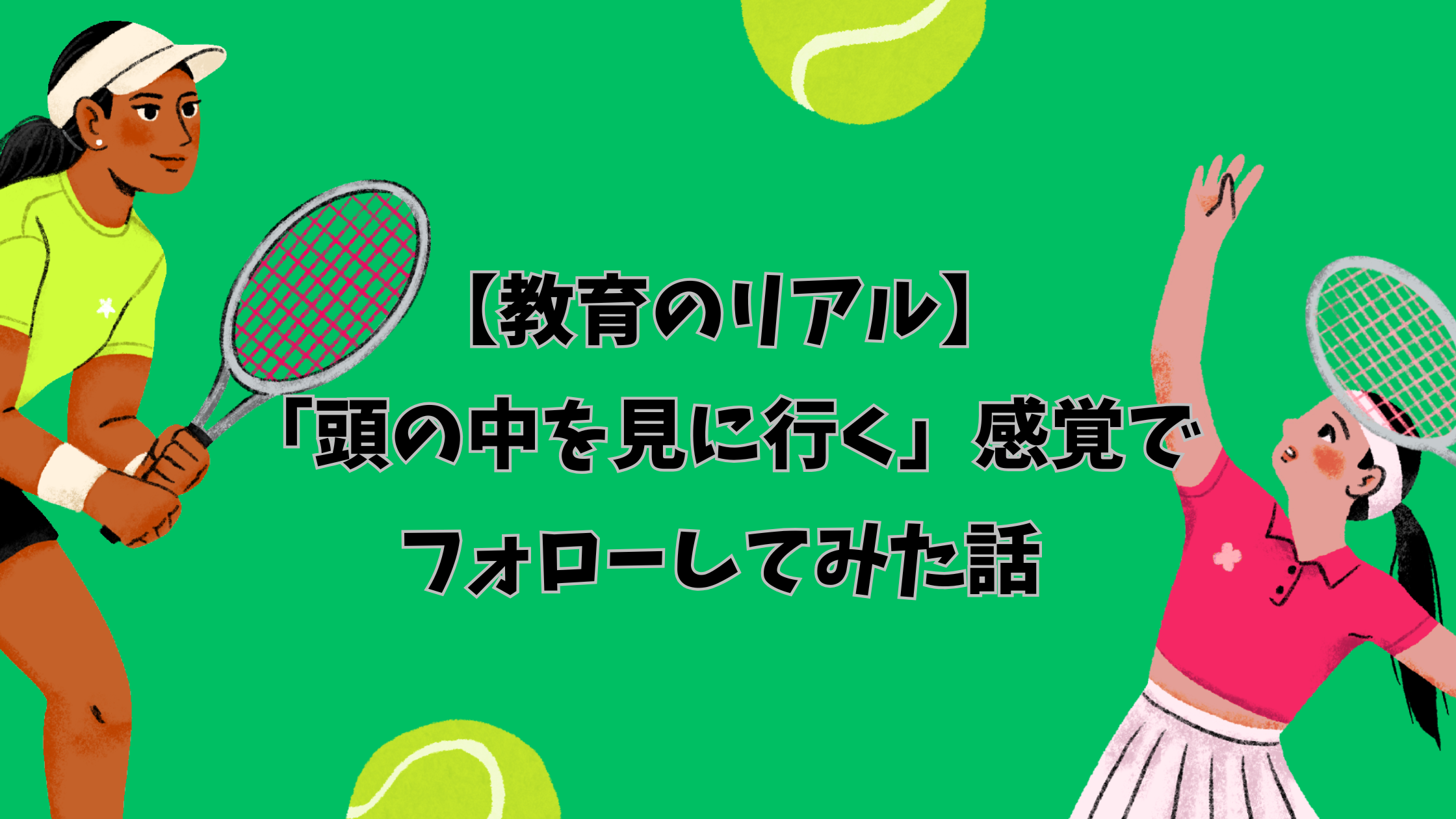

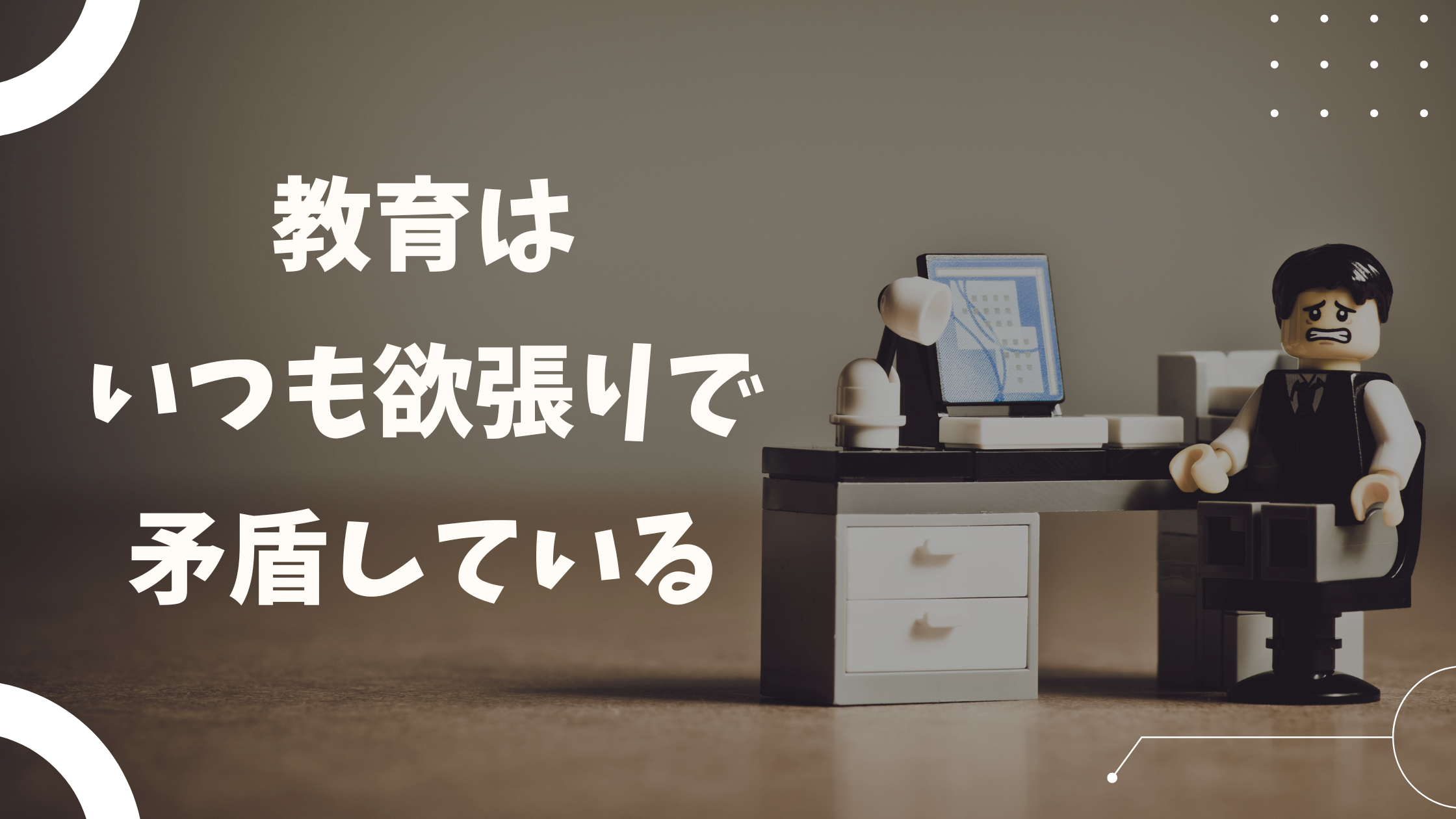

コメント