情報が集まる理由
私は普段から、教育対象者の日々の挑戦や挑戦後の感想を聞くようにしています。
他には、プリやフォローしていたスタッフからどうだったか聞くようにしています。
人によっては、「まだあの子は理解していないよ。」「質問したら答えられなくて泣いたよ」などの情報も入ります。
プラスの面も、マイナスな面も全て受け止めます。
話の中で、小さな違和感や、疑問点には具体的な内容を確認するようにしています。
どのスタッフでも、私に「これ、伝えてもいいかな?」と思える関係をつくること。
その積み重ねが、現場での“鮮度の高い情報”を集める土台になると思っています。
信頼関係がつくる早期介入
スタッフの表情、反応、声のトーン、仕事中の仕草。
それらの小さな“歪み”を感じた瞬間に、私は声をかけ、「大丈夫じゃない」と判断した場合は支援を考えます。
また、他のスタッフやプリセプターから教育対象者が心配だと報告が上がったら、すぐに対応します。
教育メンバーの担当に院内メールで対応の依頼と、対応内容を報告してもらいます。
教育は育てるだけではなく、SOSの介入や対策も早期に行うことで、教育対象者からの信頼が得られる思っていますし、それも役割だと思います。
つまり、スタッフへの介入の速さが、教育委員が信頼されるかを問われるのではないか、と思います。
今できる最善を選ぶという姿勢
「たられば」を考えても、状況は変わりません。
私はいつも、「今、何ができるか」に焦点を当てます。
信頼があるから情報が早く届く。
情報が早いから手を打てる。
その循環が現場の穏やかさと前進を生み出す。
教育は“仕組み”であり、“人と人の呼吸”でもあります。
これからも、信頼の情報網を大切にしながら「早く動ける教育者」でありたいと思います。
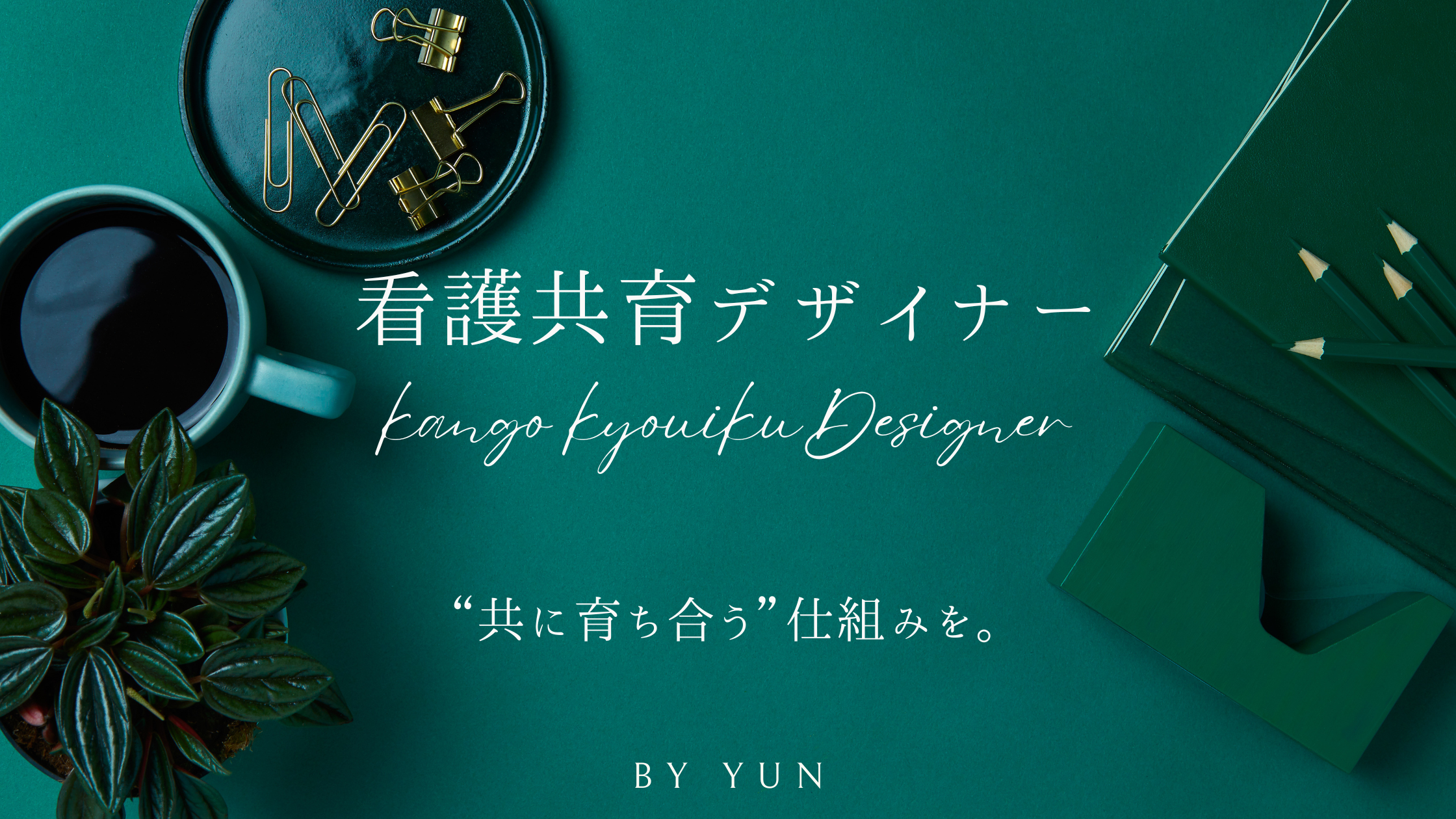
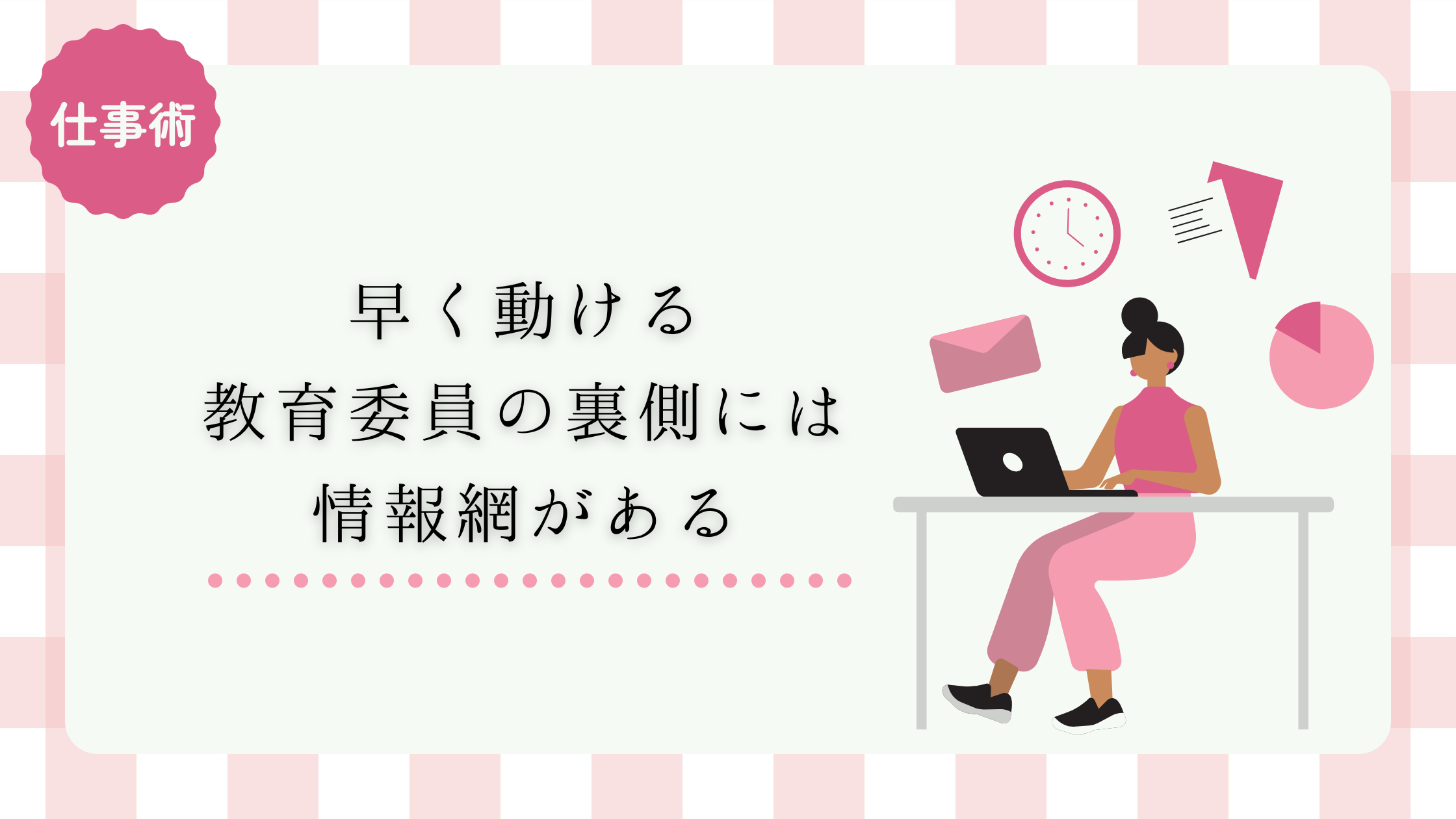

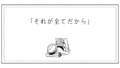
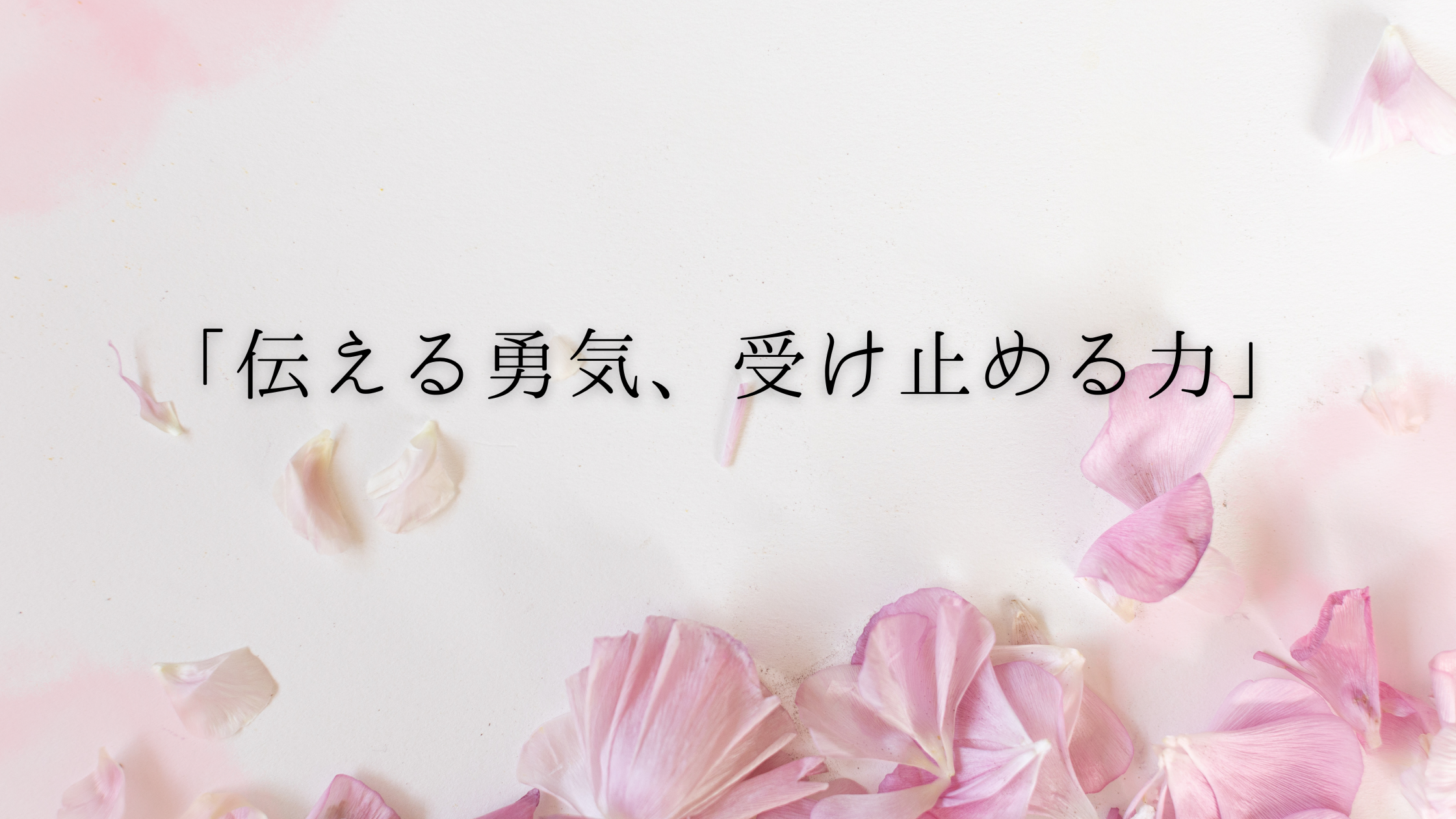
コメント