― 求めすぎない関わりが育成につながる ―
はじめに
新人教育では「できることを増やす」ことも大切ですが、
それ以上に“考える力”を育てること”が重要だと感じています。
ただ、現場は時間との勝負。
重症患者を受け持つ日や緊急対応が続くと、つい答えを教えてしまったり、
「なんでできないの?」と焦る気持ちになることもあります。
この記事では、私が最近経験した事例をもとに、
「問いかけ型教育」を意識した関わり方についてまとめます。
2年目スタッフが重症患者を受け持った日
術後4日目の患者さん。
IABPは術後2日目に抜去、CHDFも離脱予定。
ただし循環・呼吸ともに不安定で、FiO₂は100%まで上げていました。
この日は2年目スタッフがメインで受け持ち。
「何がなんだかわかりません」と不安を口にしていました。
当然です。状態は複雑で、私自身もすぐに判断に迷う場面があるほどでした。
ここで私が意識したのは、
「全部やってあげない」「でも放置もしない(9割サポートでしたが…)」というバランスです。
安全を最優先しつつ、考えるチャンスは奪わないようにしました。
「求めすぎない教育」の大切さ
以前の私は、「できることが増えること=成長」と考えていました。
でも今は、“できなくても考えようとしていること”を大切にしています。
この日も、動けない場面は「今やって」と具体的に伝えました。
それだけで、相手は迷わず動けるようになります。
そして、たとえ答えが出せなくても、
一生懸命考えて答えようとしてくれる姿勢はしっかり褒めるようにしました。
「できないことを責めるより、考えたプロセスを評価する」
それが、心理的安全性を守る教育につながると感じています。
わからないことを言葉にする力
この日の振り返りで、私はこう伝えました。
「わからないことは、恥ずかしがらずに言葉にしてね。」
見たことがない呼吸器、複雑な点滴管理、次々と出る医師指示…。
こうした状況は、これからも必ず起こります。
だからこそ、解剖や病態を理解して受け持つことが大切です。
そして、わからないことを言わなければ、私は適切に指導できません。
「わからないことがわからない」という状態でもいいんです。
それでも、「漠然とわからない」でもいいから、まずは声に出すことをお願いしました。
「言葉にする」ことで、初めて一緒に考えられるし、次につながる学びになります。
問いかけ型で育てる
問いかけは、後輩が「自分で考える習慣」を身につける最強のツールです。
例えば、こんな質問を投げかけます
- 「この患者さんで一番大事な観察って何だと思う?」
- 「この薬は何のために投与しているんだろう?」
- 「もし血圧が下がったら、まず何を考える?」
問いかけるだけで、頭の中に「考えるきっかけ」が生まれます。
その積み重ねが、次の症例で活かせる応用力になります。
まとめ
- できることを増やしながら、考える力も育てる
- わからないことは恥ずかしがらず、まず言葉にする
- 問いかけて考えるきっかけを与える
- 学びはその場で完結させず、次回の経験につなげる
教育は「教える」より「一緒に考える」こと。
そして、教える側も一緒に成長できるのが、この仕事の面白さだと感じています。
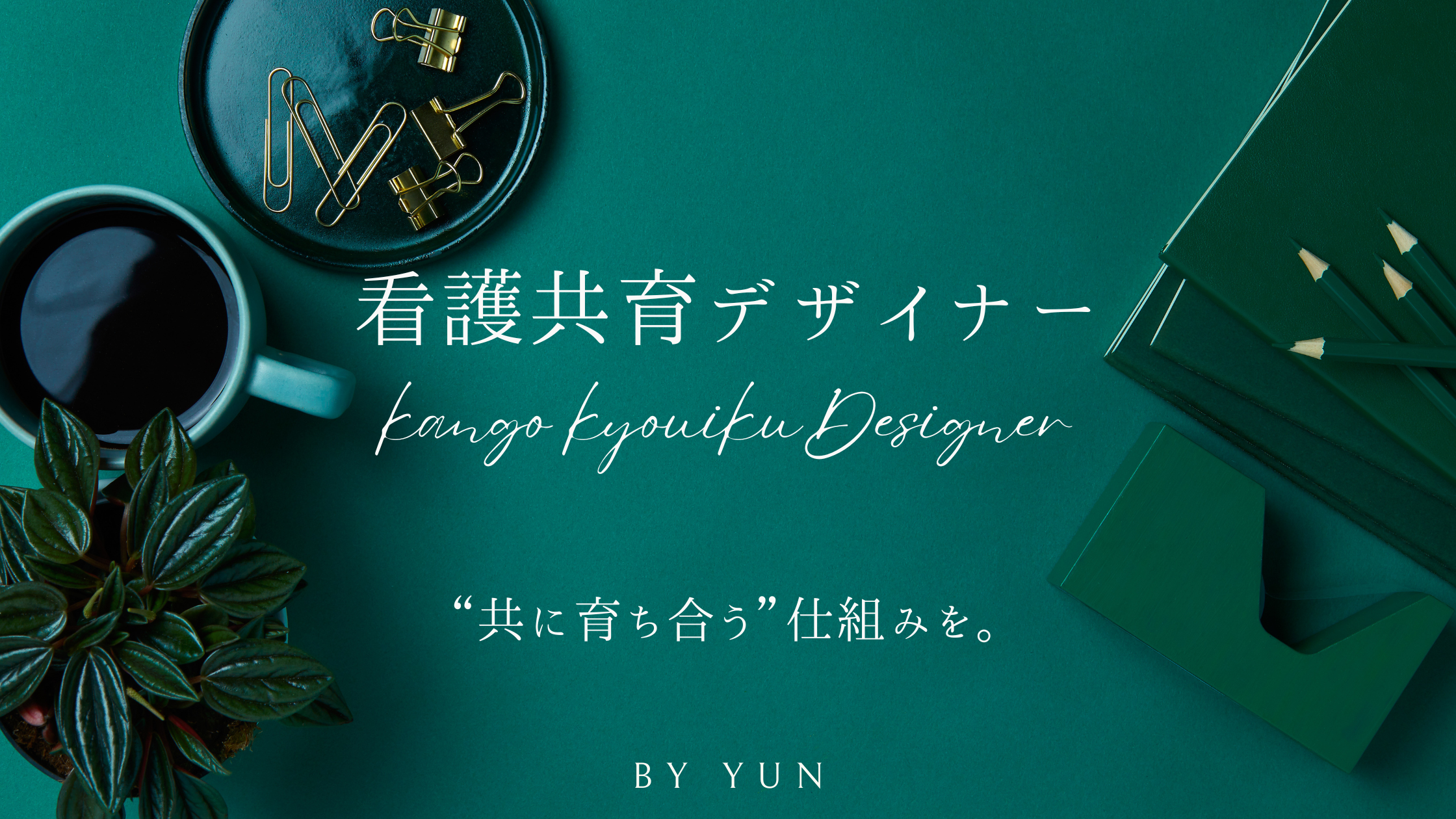


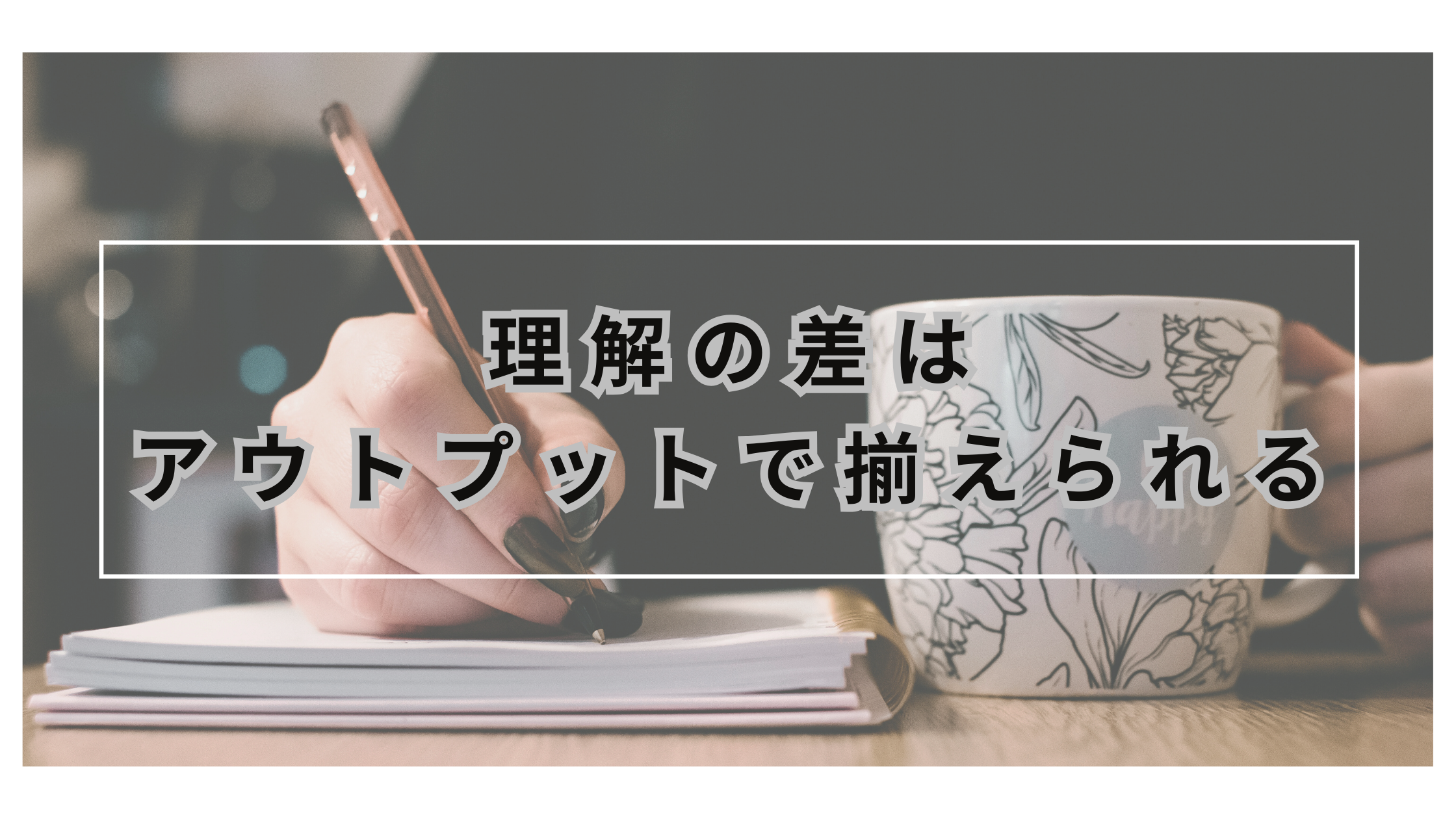
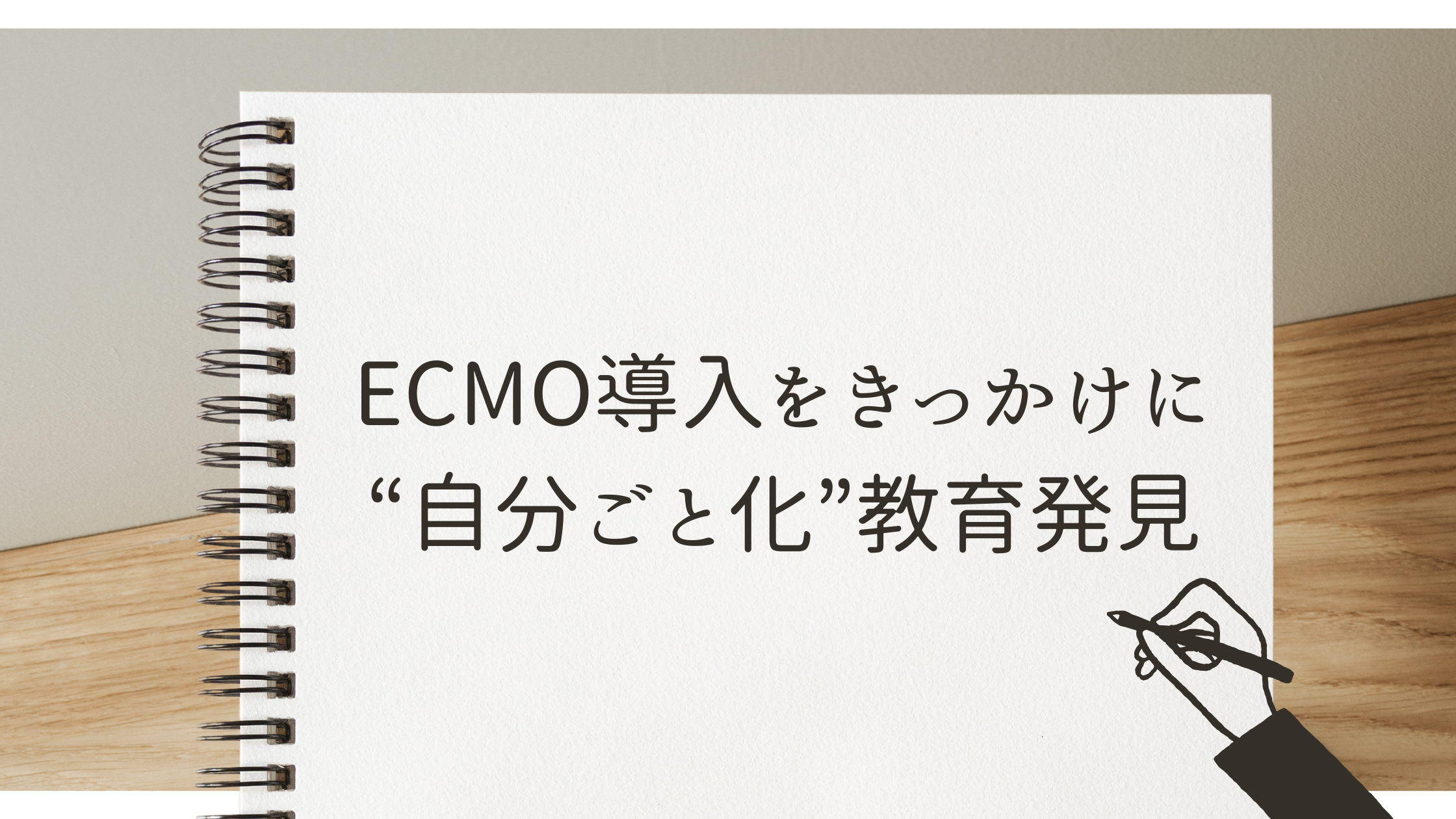
コメント