誰かのSOSが届く
「新人さんが泣いている」「プリセプターが困っている」
そんな報告が上がってきたとき、教育委員として、私は必ず動きます。
なぜなら、それが“教育する側の責任”であり、“安心をデザインする役割”だと思っているからです。
小さな声に気づけるのが、教育委員の力
教育委員に届くのは、「直接的なSOS」ばかりではありません。
むしろ、「なんとなく様子がおかしい」「ちょっとしんどそう」といった曖昧なサインや、間接的な報告が多いのが現実です。
そうした“声なき声”にも、私たちは応えていく必要があります。
対応のスピードが、安心をつくる
私は、スタッフの「困っている」を受け取ったら即座に動きます。
今回も、教育メンバーから「プリセプター以外の役割が多すぎてしんどい」という報告があり、すぐに師長へ共有。
役割の偏りについての見直しを依頼しました。
結果、役割の再配分が行われ、負担の軽減につながりました。
教育委員=橋渡し役であり、守る人
教育メンバーが動かなかったときは、必ず確認します。
たとえ年上のスタッフであっても、なぜ動かないのか。
「スタッフの気持ちはどうなるのか?」「教育担当とは何のためにいるのか?」
私は、そう問い続けています。
病棟全体で支える仕組みづくり
今回の件では、本人にも確認し、「こういうときに負担を感じます」と明確に言葉にしてくれました。
その言葉を尊重し、「教育方針として病棟全体に案内しよう」と提案。
本人からも「お願いします」と返ってきました。
さっそく、病棟全体にメールで共有し、采配時の早見表にもコメントを追加しました。
教育は、仕組みと信頼で守れる
スタッフが安心して「助けて」と言えるように。
教育委員が、その声をちゃんと受け止め、連携して仕組みに変えていく。
そんな現場を、これからも丁寧にデザインしていきたいと思っています。
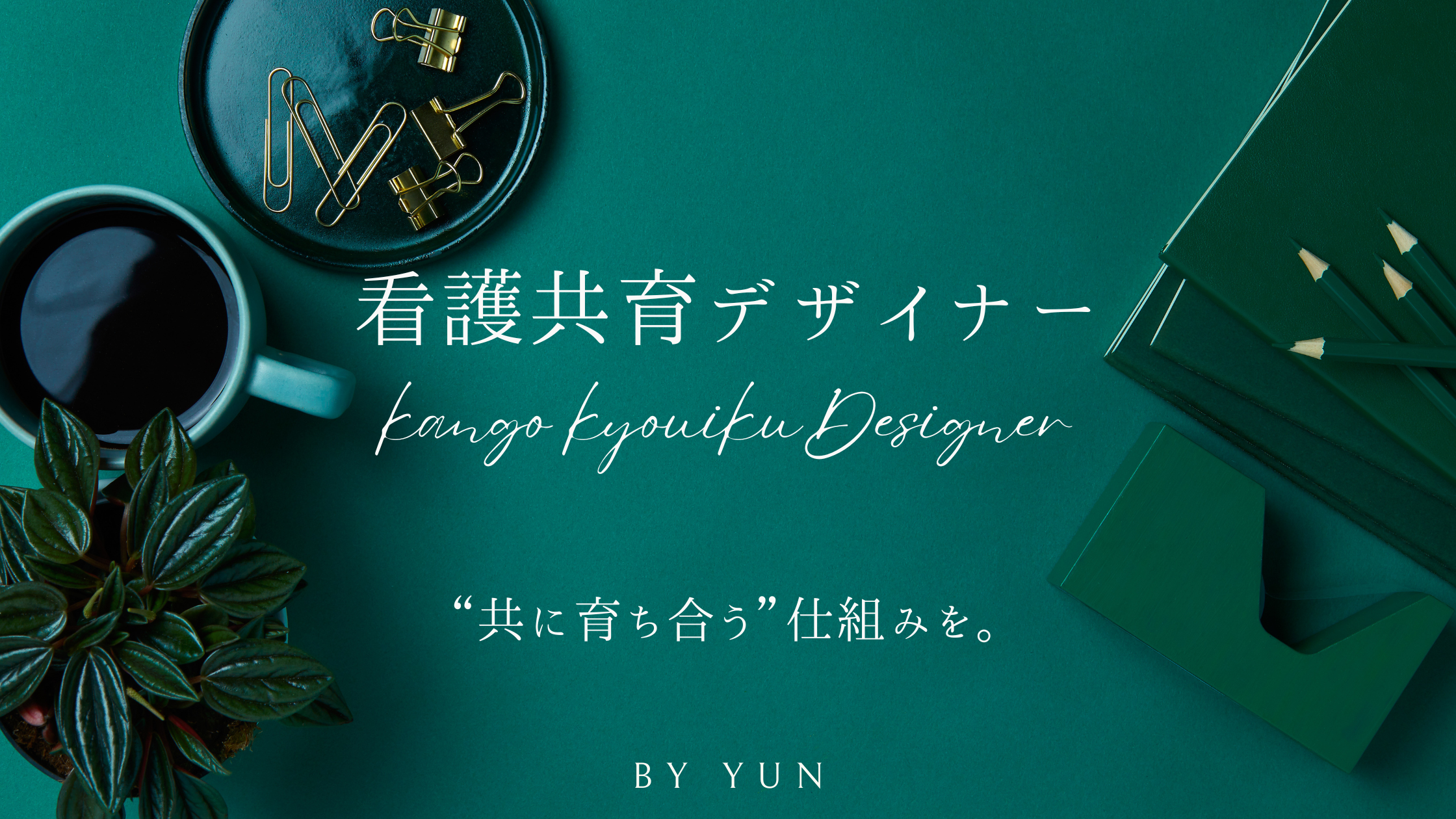
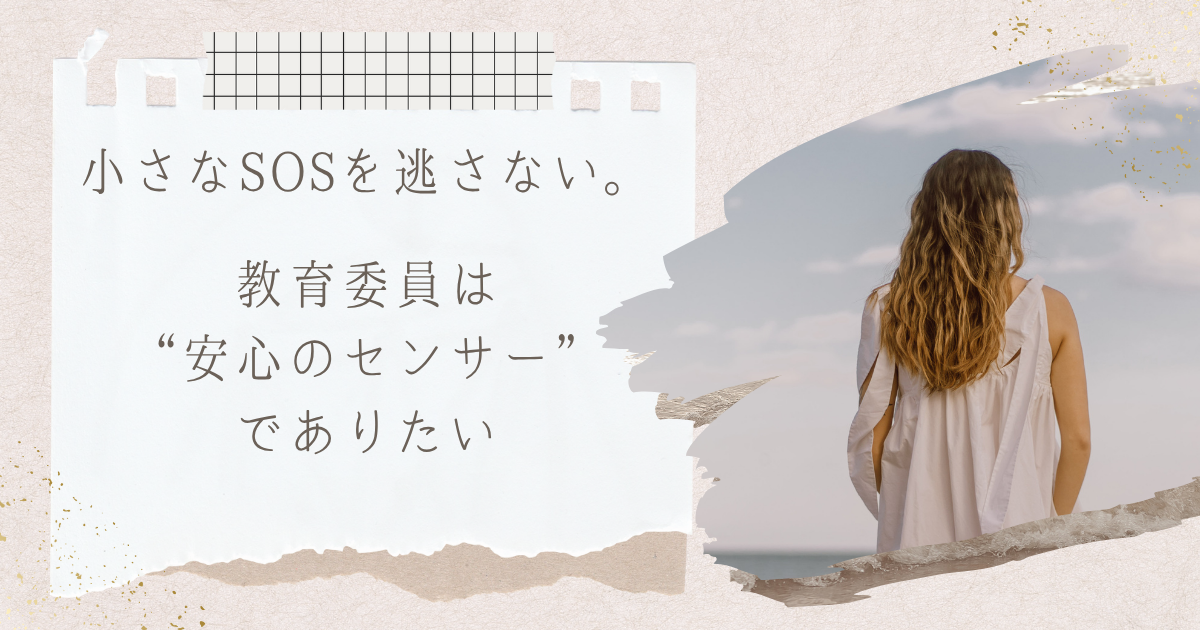


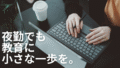
コメント