はじめに:育ちの違いに悩むとき
「どうしてこの子は、経験を積んでも成長が見えにくいのだろう?」
教育をしていて、そんなふうに感じる場面があります。
同じ時期に入職したスタッフでも、見るからに成長している子もいれば、同じ場所にずっと立ち止まっているように見える子もいる。
その差は何なのか。
最近、私はそれが 「課題を持てるかどうか」 に大きく関係しているのではないかと感じています。
課題を持てないままでは、成長が止まる?
課題を持てないまま働いていると、
- 「自分が今、どこまでできていて、何を伸ばすべきか」がわからない
- 振り返りをしていても実感が伴わない
- 看護をしていても、どこに注意するのかが曖昧
- 「何となく対応して終わり」が日常になる
最近関わった2年目のスタッフは、術式の理解が不十分なまま術後患者の受け持ちに入りました。
フォロースタッフに対して、フォローしてほしい内容は、
自分の課題や目標を伝えるのではなく、「困ったときに聞くので大丈夫です」と返答。
けれど「術後2日目の観察で何を意識する?」という問いには答えられませんでした。
実はこの3ヶ月、こうした状況が変わっていません。
「経験を積めば自然と成長する」とは限らないことを痛感しています。
教育者のジレンマ:課題を“渡す”だけでは足りない
教育担当と毎月面談をして、記録上では“関わっている”ように見えても、
本人が“自分の課題”として言葉にできていない限り、学びは蓄積されていかない。
「やったほうがいいこと」を伝えても、本人の中で“必要なこと”として腑に落ちていなければ、成長にはつながりません。
課題は、単に“与える”ものではなく、
“気づいて持てるように関わる”ものなのだと感じるようになりました。
工夫してみたこと:術式別ルーブリックの導入
今回は、本人の状況に合わせて 術式に特化したルーブリック を導入してみました。
評価の観点は以下の4つです:
- 術式の理解
- 術後経過の理解
- ドレーン・鎮痛管理
- 看護の根拠
それぞれを★1~5で自己評価し、教育者ともすり合わせたうえで、
「次に★を上げるために何をするか」という具体的な目標を一緒に立てる。
この評価を使うことで、本人自身が自分の課題を明確化でき、現状からのstep upのきっかけになるのではないか?と、これまでの関わり方に追加する方針としました。
6月の目標の振り返りから実施するので、これから反応を確認するという形になります。
成長の鍵は“気づき”と“振り返り”
人は、自分の“できていないこと”にはなかなか気づけません。
これは「メタ認知(自分を客観的に見る力)」が関係していて、
成長の早いスタッフほど、この力が高い傾向にあります。
また、心理学では「ダニング=クルーガー効果」というものがあり、
スキルが低いほど、自分の能力を過信しやすいという傾向があるとも言われています。
確かに、自己評価が高いスタッフは、「できた」と評価した内容が、「何回か経験したから」という内容が薄い評価で、スキルやアセスメントが伴っていないと感じることが多いです。
だからこそ、評価の“見える化”と“対話による振り返り”が必要なんです。
育たないスタッフはいない。きっかけがあれば人は育つ
「課題を持てないスタッフは育たない」のではなく、
「課題を持つきっかけがなかっただけ」かもしれません。
育たないスタッフなんていない。
教育者の関わりひとつで、
“気づき”が生まれ、“課題”が生まれ、
その子の成長は加速していくと、私は信じています。
おわりに
私たちは毎日、業務に追われながらも「誰かの成長」に関わっています。
だからこそ、ただ「教える」だけでなく、
“気づける仕組み”や“振り返る場”をつくっていくことが、
教育者としての大事な役割なんだと、あらためて感じた日でした。
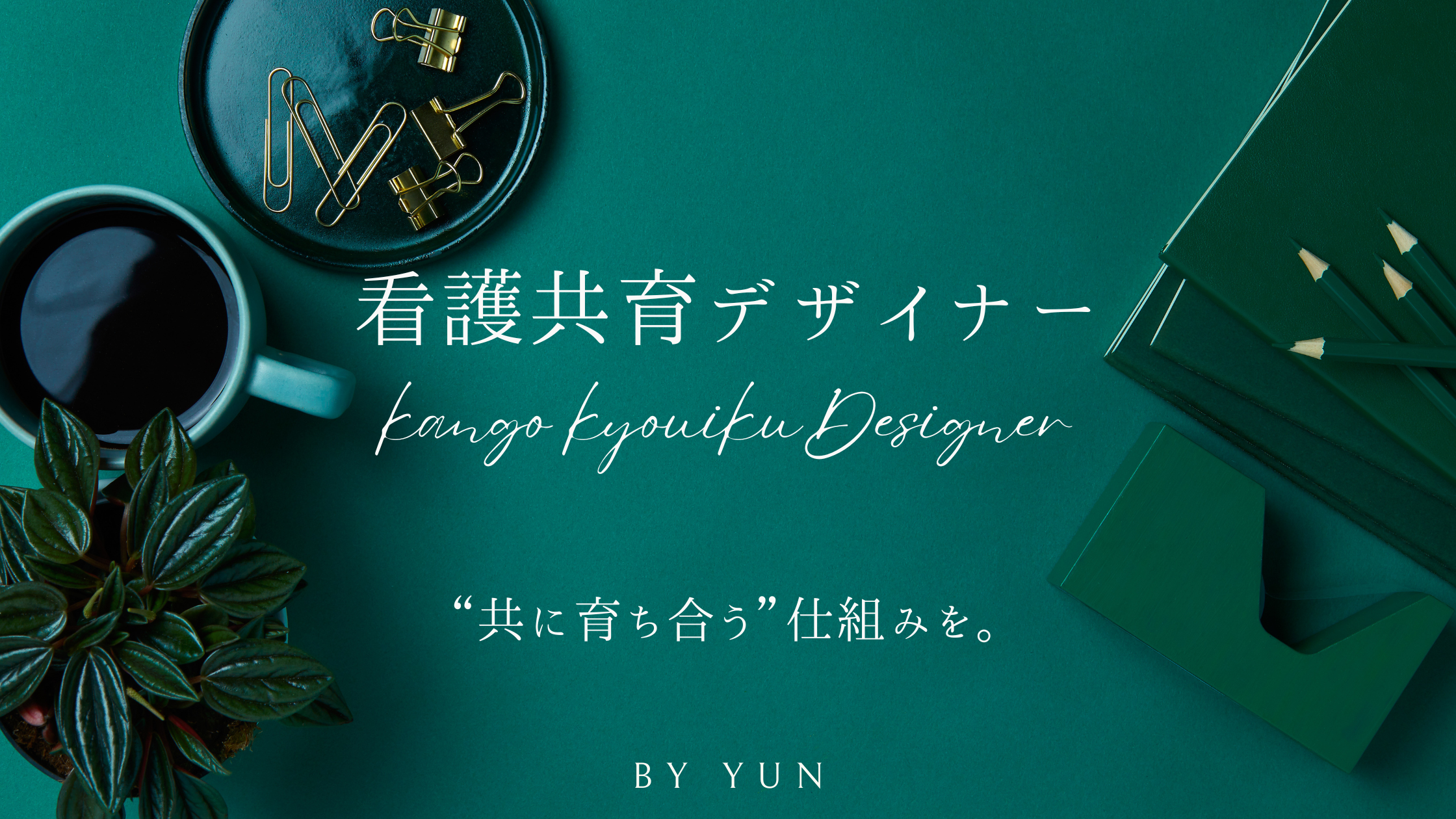
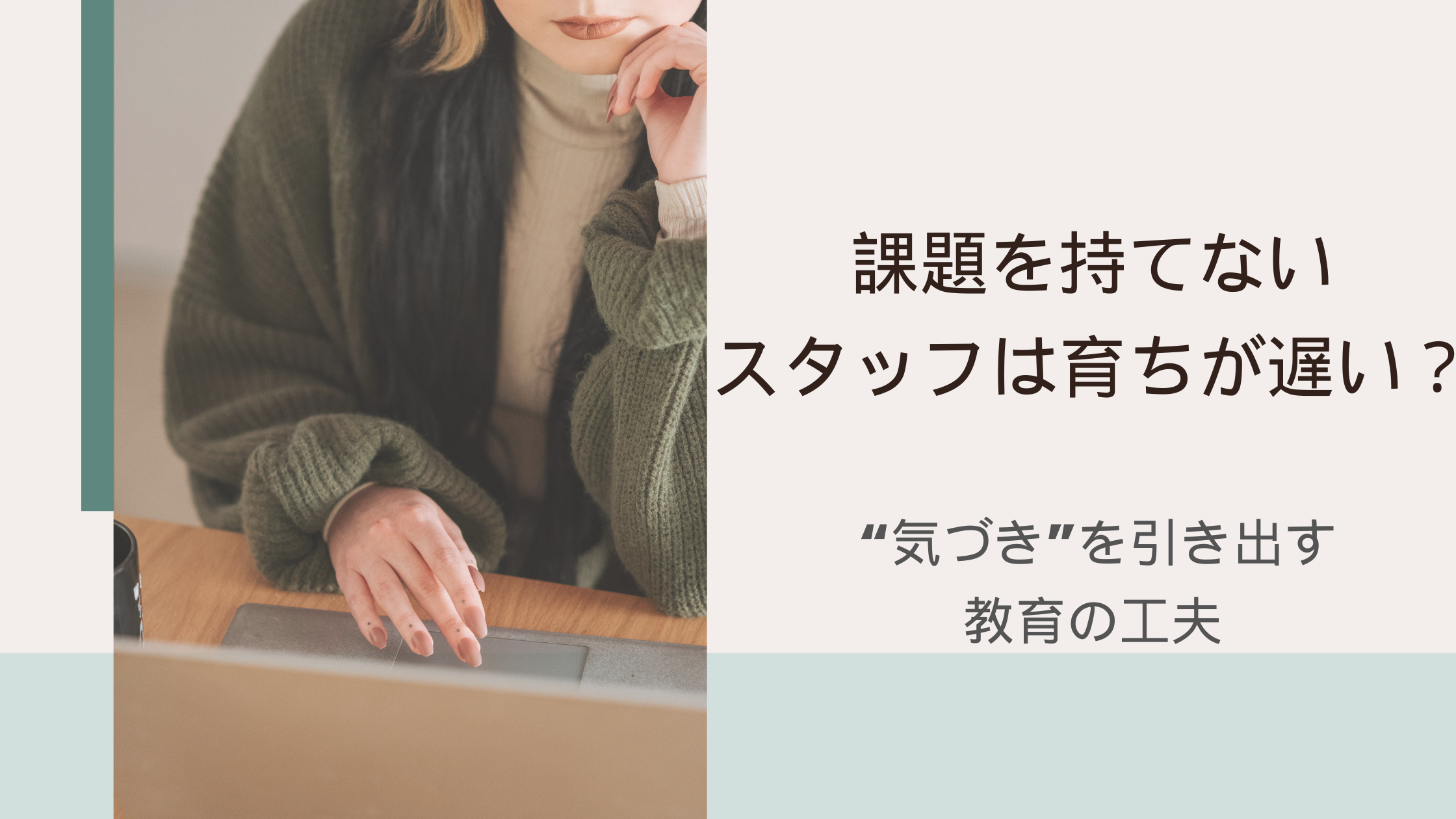

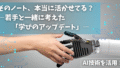
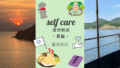
コメント