最近の教育の悩み
新人教育や2年目、病棟全体の教育サポートをしていると、
「この子はあともう少しで自立できるな」というスタッフと、
「自分ではできていると思っているけど、実はまだ危ういな」と感じるスタッフがいます。
私たち教育担当は、いつもその差に悩みながら、「じゃあ、この2人に同じ機会を提供するのが本当に“平等”なのかな?」と考えるようになりました。
平等より“公平”が大事と気づいた背景
以前は「同じように機会を与えなければ不公平」と思っていました。
でも、現場では“同じように教えても同じように伸びるわけじゃない”というのが現実です。
そのことに気づいてから、私はこう考えるようになりました。
先に自立できる人から自立させる。
成長のスピードや姿勢を見て、“今”必要な教育介入を変える。
それって、平等ではなく“公平”を目指す教育なんだと思います。
頑張ってる“つもり”と、本当に努力している人の違い
「なんで私だけ確認テストを受けるんですか?」
そんなふうに言われたこともあります。
でもそれは、
- アセスメントが不十分
- 質問が多いのに、自分で考える姿勢がない
- 自己評価が高くて現状に気づいていない
そんな背景があるからこそ、確認テストというツールが必要なんです。
逆に、普段からきちんと振り返りができていて、人の責任にせず自分で成長しようとするスタッフには、わざわざテストを課す必要がないと判断しています。
ですが、確認テスト開始後は、すべての教育対象者に実施をするように決めました。
自分は教育委員だけど、関わらない選択もある
教育って、正直感情にも左右されます。
私は、雑な仕事、何度指導しても変わらない、だけど自己評価だけは高いスタッフには警戒していますし、無意識に拒否反応を感じてしまうこともあります。
だからこそ、そういうスタッフには教育担当を通して関わるようにしています。
直接私が関わることで、かえってプレッシャーを与えてしまったり、私自身が求めすぎてしまうからです。
教育って、誰かの“人生に責任を持つ”こと
「この人は自立できる」と判断するということは、
命を預けるに値する人材かどうかを見極めているということ。
それはとても重たい責任です。
だから私は、感覚ではなく、確認テストやルーブリック、日々の振り返りを通して、
「自立しても大丈夫」と自信を持って判断できる材料を揃えるようにしています。
伝わってなくても、支えてるからこそ
たぶん、教育対象のスタッフたちは、
私たちがここまで環境調整やフォロー体制を整えていることなんて気づいていません。
でも、それでいいんです。
いつか自分が教育する側になったときに、
「あのとき、支えてもらってたんだな」って気づけたら。
それまで私たちは、“気づかれない努力”を積み重ねていきます。
それが、教育の仕事だと思うから。
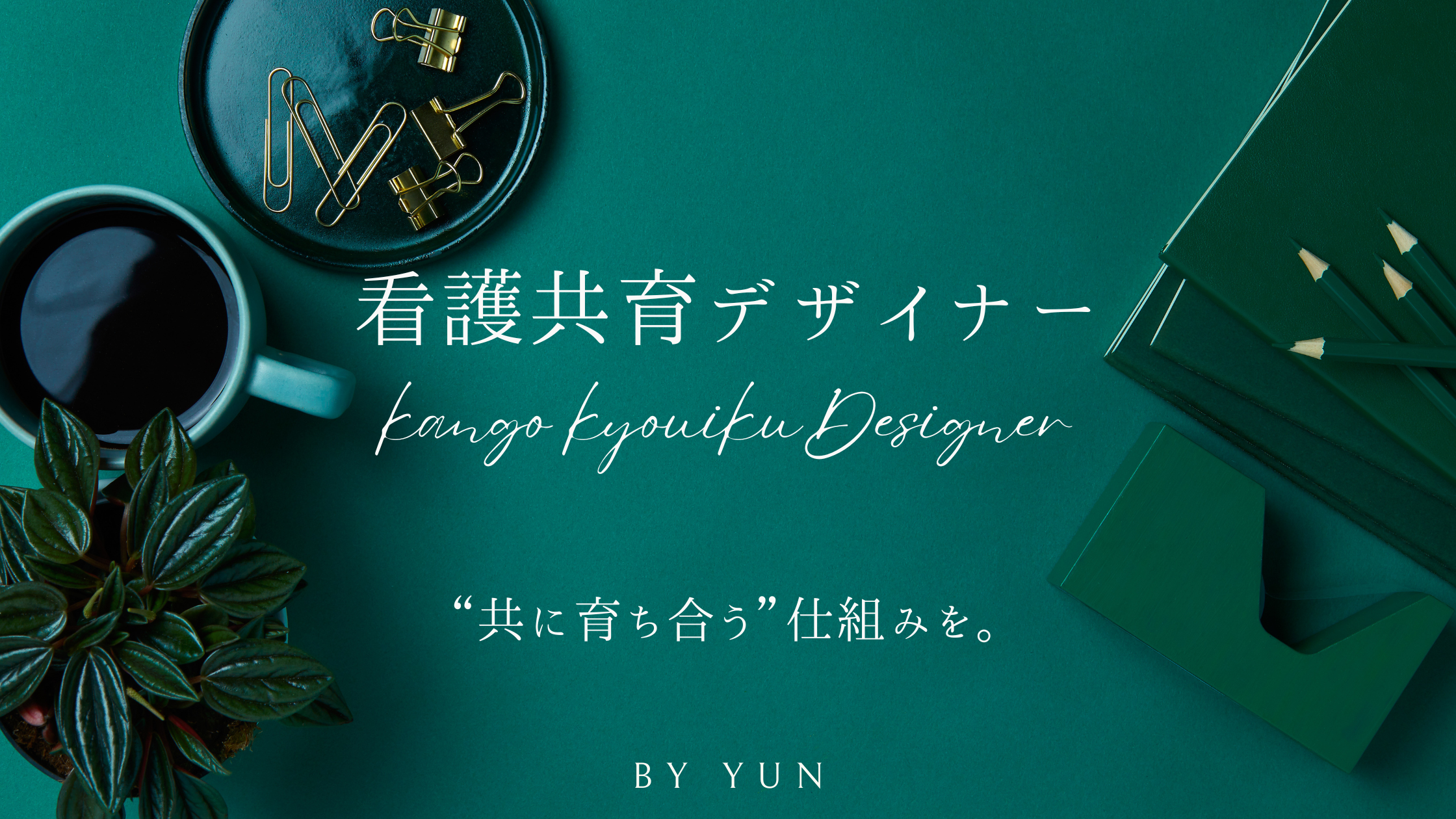
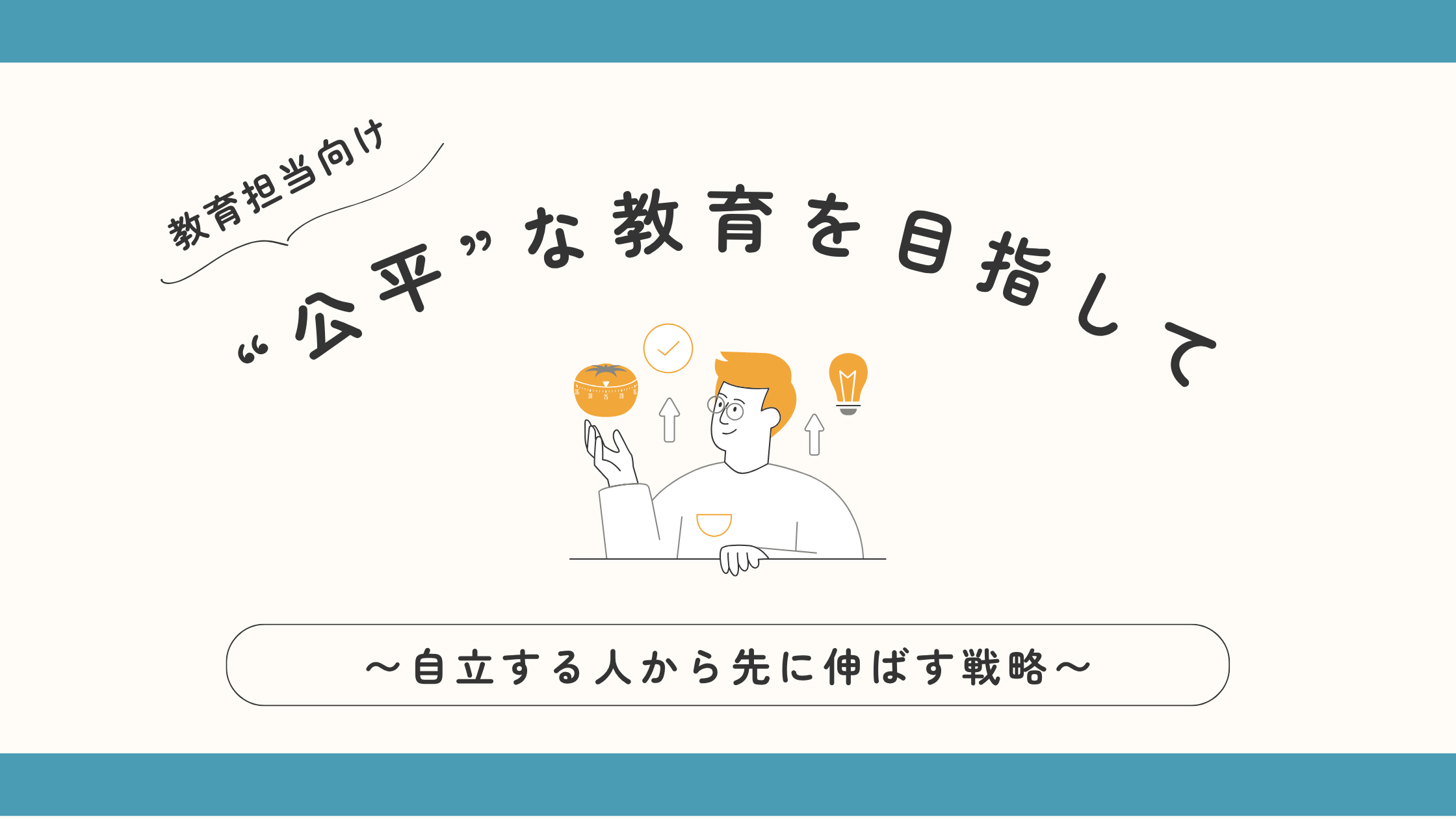

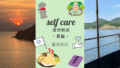
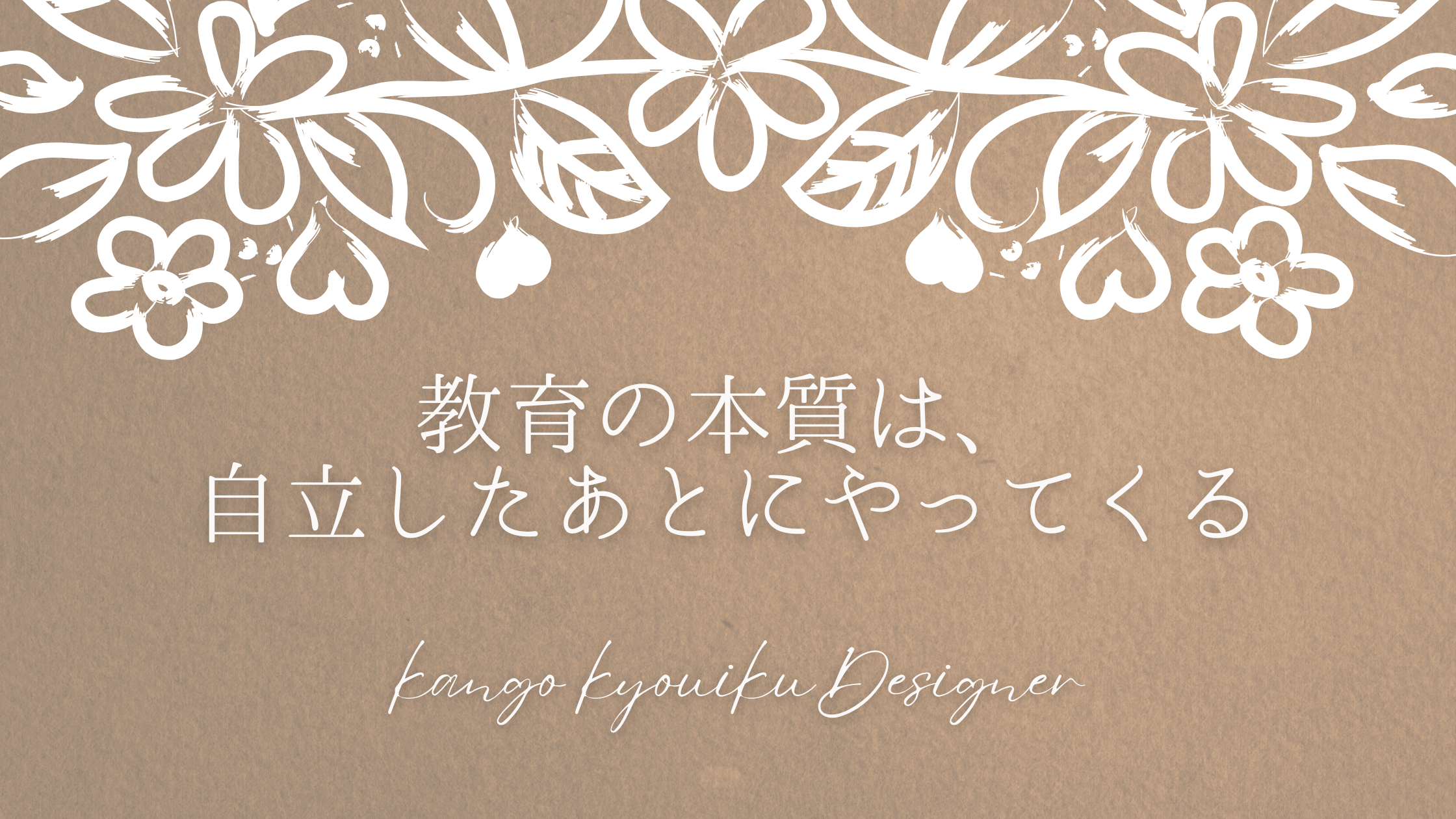
コメント