〜 ICU異動スタッフの壁 〜
ICUに異動した、一人のスタッフがいます。
そのスタッフは50代で、これまで一般病棟で長く働き、経験も豊富でした。
でも、今回ICUに異動し、想像以上に「できない自分」に直面したようでした。
今までできていたことができない
一般病棟では慣れた手つきで、判断も早く、周囲にも強く言える存在だった。
だけどICUに来ると、物品の場所も違い、患者さんの重症度も違い、ICUならではのルールや手順もある。
「なんでこんなこともわからないんだろう」
「一般病棟ではできていたのに、なんでこんなに時間がかかるんだろう」
そんな“できない自分”に戸惑い、気持ちも落ち込み、時にはイライラした態度になってしまうこともありました。
年齢・経験は関係ない
この経験を通して改めて感じたのは、
「何歳でも、どれだけ経験があっても、初めての環境では誰でも壁にぶつかる」 ということ。
できない自分に出会ったとき、人は落ち込むし、自信をなくすことがある。
それは、新人もベテランも同じです。
焦らず、期待しすぎず、確実に
本来なら、異動から3ヶ月で夜勤見習いに入る予定でした。
でも、本人の表情や業務への不安、周囲のスタッフの声を踏まえて、教育担当やプリセプターと話し合い、夜勤見習いのスタートを延期することを決めました。
夜勤に入ることがゴールではない。
「安全に」「安心して」「本人が前向きに」進めることが、何より大切だと思ったからです。
一番大事なのは、環境を整えること
人は、できない自分に出会ったとき、強がることもあるし、落ち込むこともある。
そんな時、放置するのではなく、適切な声かけと環境を整えることが教育の一つだと改めて実感しました。
本人のペースを尊重しながら、必要なサポートを届けること。
焦らず、期待しすぎず、確実に。
教育者として感じたこと
壁にぶつかるということは、伸びしろがあるということ。
できない自分にモヤモヤしたり、イライラしたり、自分を責めたりするのは自然なことです。
だからこそ、教育者として、
その“しんどい気持ち”をどうサポートするか。
心が折れないように、仕事を休む選択をしなくて済むように、どう支えるか。
教育者は、課題を乗り越えさせるだけでなく、
「その人の気持ちを守る存在」でありたいと、私は思います。
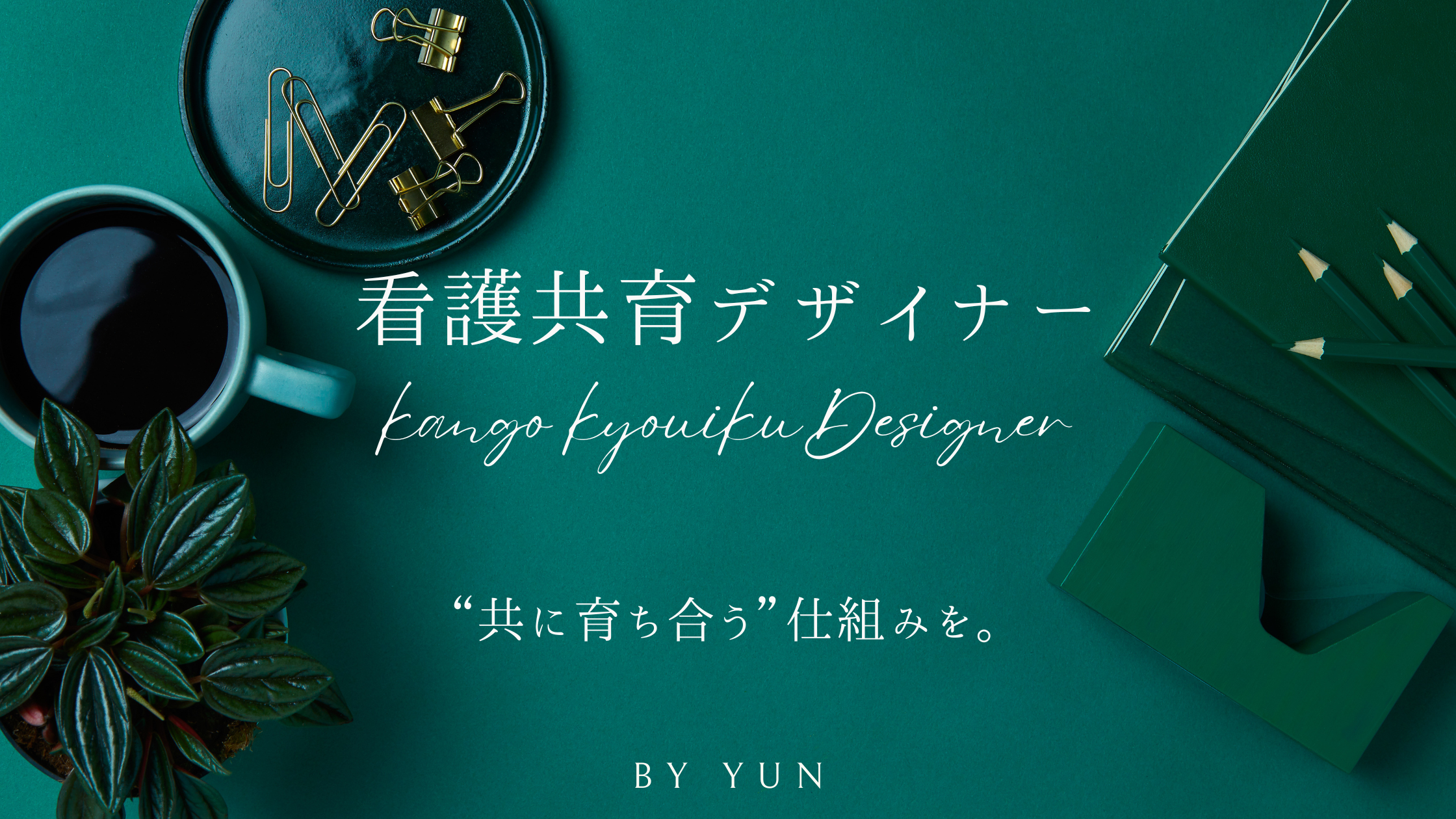


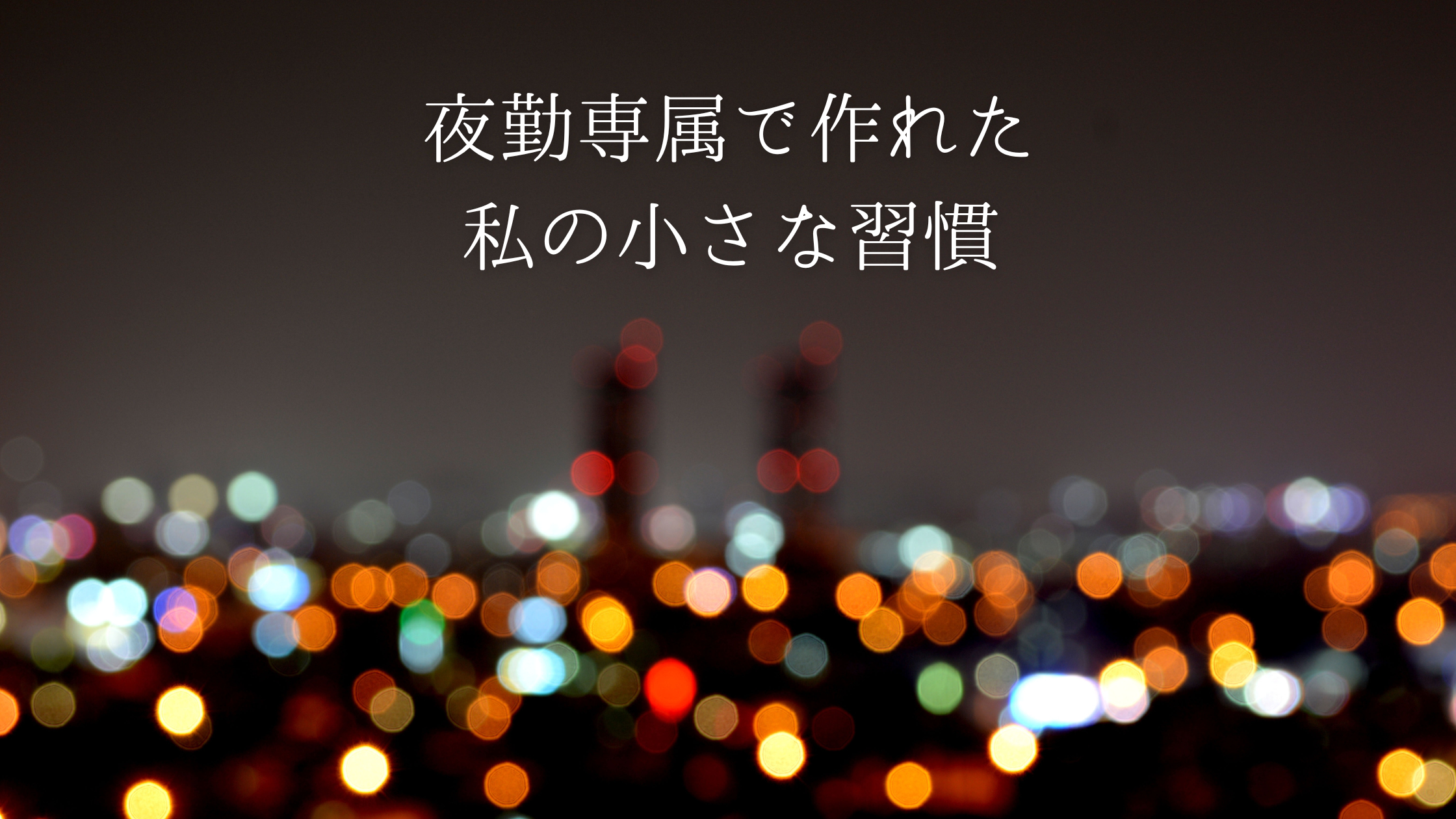
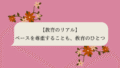
コメント