「早く進むこと」が正解じゃない
教育って、
できるようになるために早くステップアップすることが良い、と思われがち。
でも、本当にそれでいいのかな?
私は最近、改めて考えるきっかけがありました。
産休明けのスタッフとのやりとり
3月、産休・育休明けで復帰したスタッフがいました。
5年以上ブランクがある、40代のスタッフ。
物事ははっきり言えるけれど、不安が強い方でした。
周りから見たら、「もう十分できてる」「次に進んでいいよ」と思うレベル。
でも、本人は「まだできていない」と思い込んでいる。
プリセプターは、以前一緒に働いたことのある教育委員。
だけど、その教育兼プリ担当が
「次は術後の受け入れをしよう」と、どんどん進めようとしていました。
本人の気持ちは、そこに全くついてきていなかったのです。
本人の「不安」を置き去りにしない
そのままstep upして進ませようとした時、私は違和感を感じました。
いくら経験年数があっても、
いくら「できているように見えても」
本人が納得していなければ、モチベーションは下がるし、前向きに学べない。
そこで本人に、こう提案しました。
「術後1日目の患者さんを、フォローをしっかりつけたうえで、まずは自信を持って受け持てるようにしませんか?」
すると、本人は素直に本音を話してくれました。
「実は私、術後患者さんをまともに看護できていないのに、TAVIなどを受けろって言われるのが、本当に嫌だったんです。カテーテルと同じ感じだからと言われても、気持ちがついていかない…。」
本人の気持ちを聴くことができたこと。
私はとても嬉しく感じました。
実は、私より5歳以上年上のスタッフです。私もそのスタッフとお話をするのは、緊張します。
相手からしたら、年下のスタッフに言われているって思われないかな、などもちろん気にします。
ですが、すべて相手を思った、教育委員としての提案です。
その人に合ったスピードで進む
教育委員としては、
「早くできるようになってもらわなきゃ」
「夜勤の人数足りないし、早く一人前になってほしい」
そう思う場面も、現実としてあります。
だけど、
本人の気持ちが置き去りになった教育は、続かない。
本人が「よし、やってみよう」と思える環境を作ることが、
一番の近道なのかもしれない。
まとめ
教育って、焦らせることじゃない。
その人のペースに合わせることも、教育の大事な要素。
今回は、本人の「今の気持ち」に寄り添いながら、
少しずつ自信を積み重ねて、
その先に自然と「次のステップに進みたい」と思えるような関わりを目指しました。
私も、日々学びです。
✔️ この記事のメッセージ
- 本人の気持ちを置き去りにしない
- 教育のスピードは人それぞれ
- 教育者も「聴く力」と「提案する力」が大切
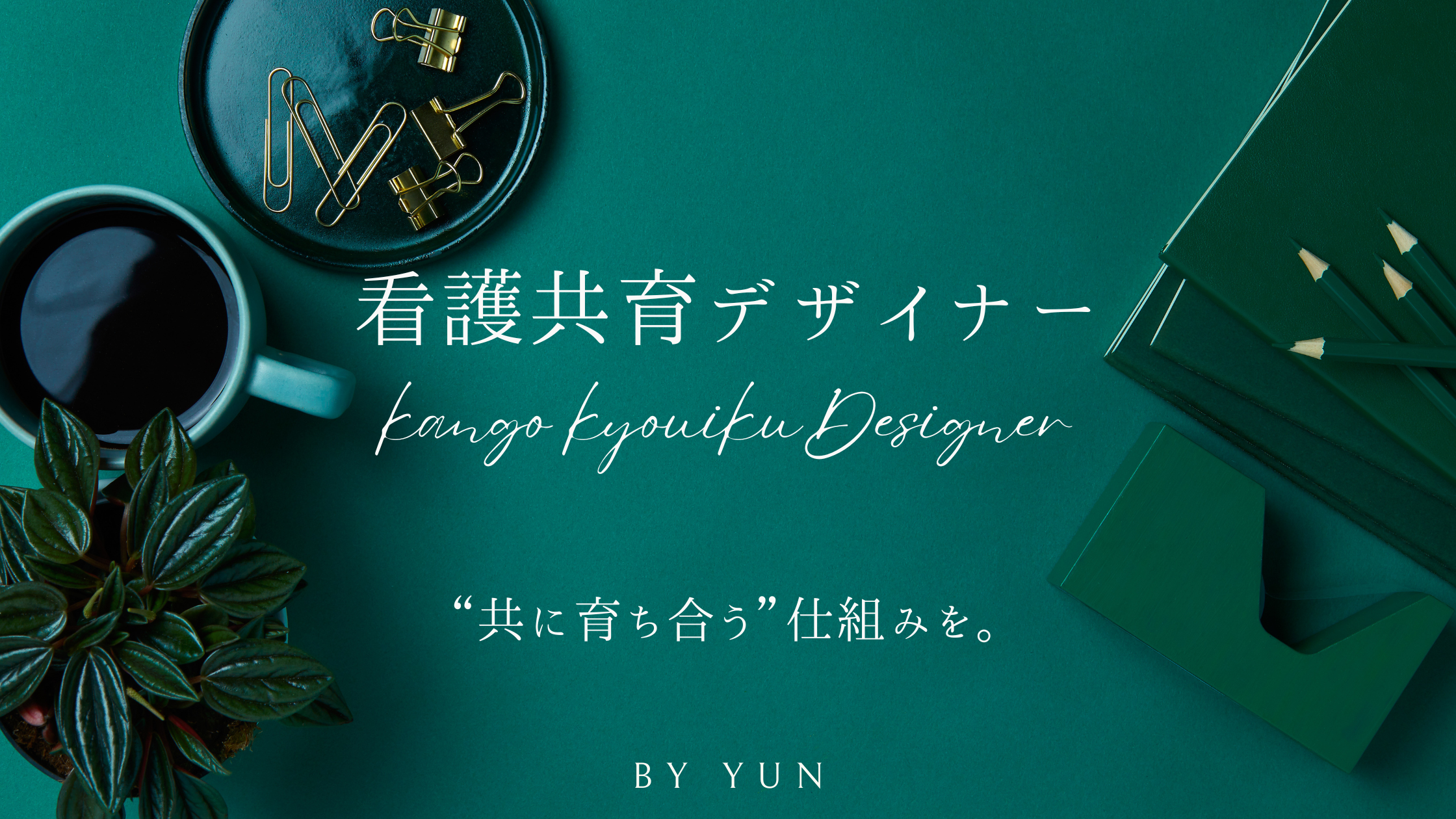
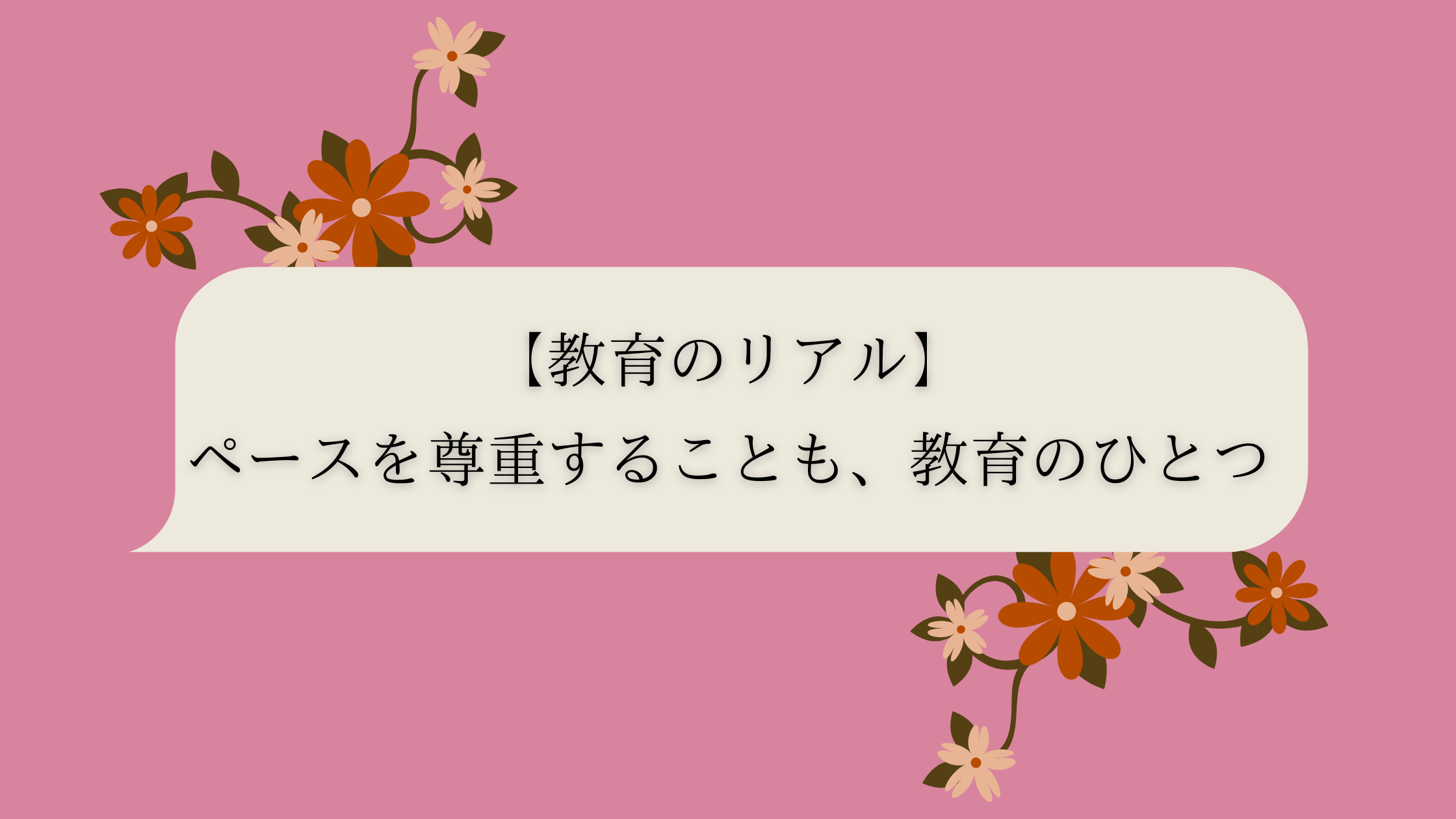

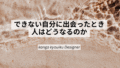
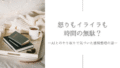
コメント