居酒屋で教えた経験が、今の看護教育観を育てた
初めて人に「教える」という役割を担ったのは、大学時代の居酒屋のアルバイトでした。
最初は自分が必死で覚えることで精一杯だったはずが、
気がつけば、新しく入ったスタッフに業務を教える立場になっていました。
私にとってそれは、“教えること”の喜びと、同時に難しさを知る大きなきっかけだったと思います。
教えることって、思っていたよりずっと繊細で、相手によって全然うまくいかないこともある。
でも、だからこそ面白くて、やりがいがあって…
その経験が、今、看護の現場で教育に関わる私の土台になっています。
教えることの難しさを知った日
自分では丁寧に説明しているつもりなのに、うまく伝わらない。
ある新人スタッフには、私の言い方がきつく聞こえたようで、後から別のスタッフ経由で
「怖かったみたい」と伝えられたこともありました。
そんなつもりはなかった…と落ち込みましたが、その出来事があったからこそ、
「伝え方」や「相手の表情」を今まで以上に気にするようになりました。
同じことを教えても、相手によって反応や理解の仕方はまったく違う。
だから、「自分がこう思う」ではなく、「この人にはどう伝えたらいいだろう?」という視点を持つようになりました。
不器用だったけれど、一人ひとりと丁寧に向き合いたいという気持ちだけは、いつも大切にしていた気がします。
「声」で伝えるということ
私は、声の大きさには自信がありました。
人見知りな性格ではありましたが、居酒屋での接客中、お客さんから注文をもらったときには、
店内に響くように、でもノイズにならないように
――誰よりも通る声で、はっきりと伝えることを心がけていました。
(アナウンサーではないけど、アナウンサー気取りで、ハキハキと、イキイキと。)
「伝える」は、「伝わる」ことではじめて意味を持つ――そのことを、身体で覚えた気がします。
看護の現場に生きる“あの経験”
今、看護師として新人教育やスタッフ育成に関わる中で、あの頃の感覚がふと蘇ることがあります。
“自分の教え方がすべてではない”“相手によって伝え方を変えることが大切”
そんな教訓は、まさにアルバイト時代に身についたものでした。
そして、今の私の教育観はこうです。
「教える」は、“指示する”ことではなく、“その人らしい学びを一緒に探し、一緒に成長すること”。
それは時間も労力もかかることだけど、人が育つ喜びや変化に出会えたときの感動は、何物にも代えがたいものです。
まとめ:教えることで、自分自身も育てられてきた
アルバイトを通して学んだ“教えることの責任”と“人との関わり方”は、今の看護師としての私に確かに息づいています。
教育は、相手の成長を助けるだけでなく、自分を見つめ、磨く機会にもなる。
今後も、そんな教育者であり続けたいと思っています。
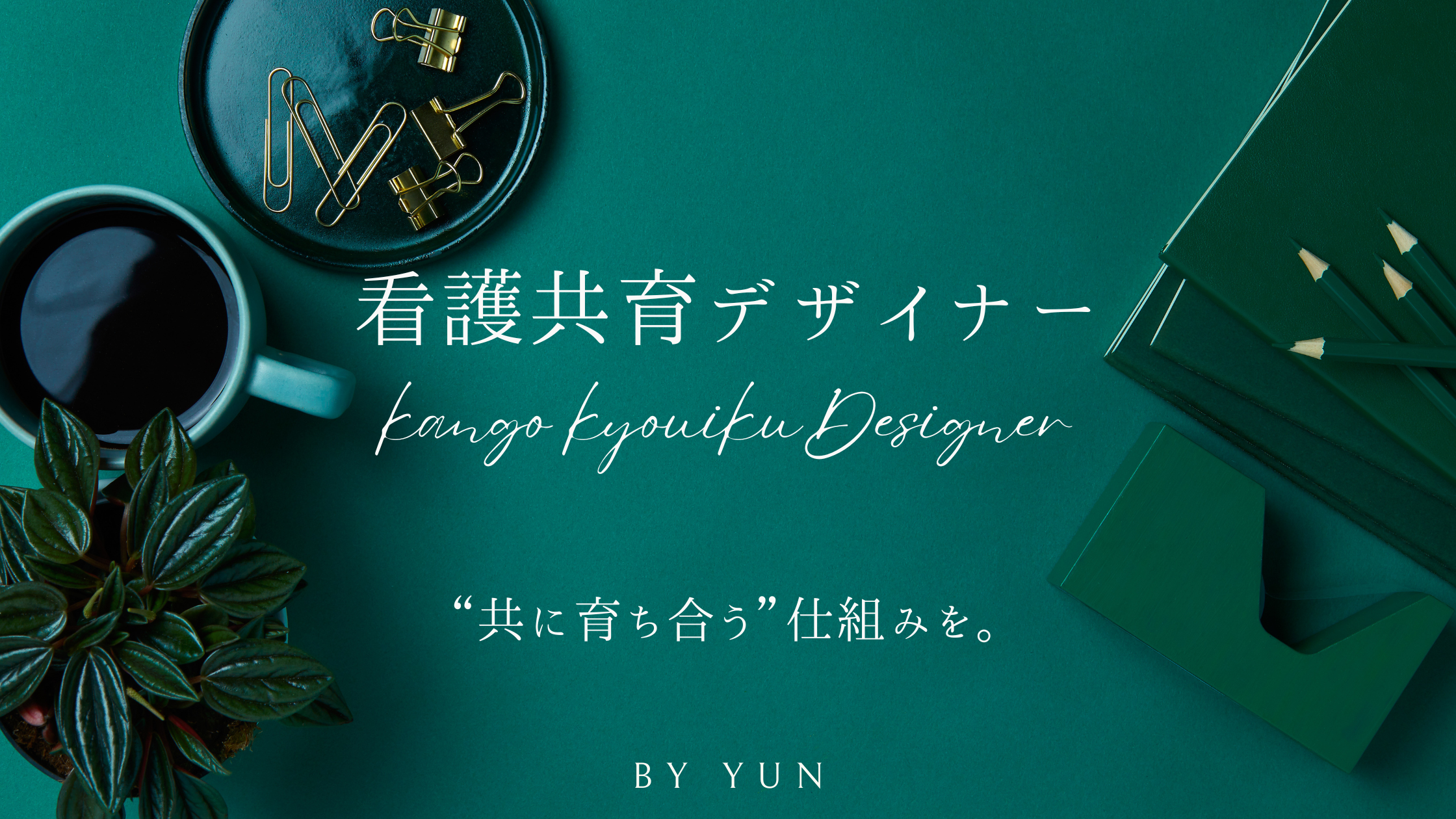
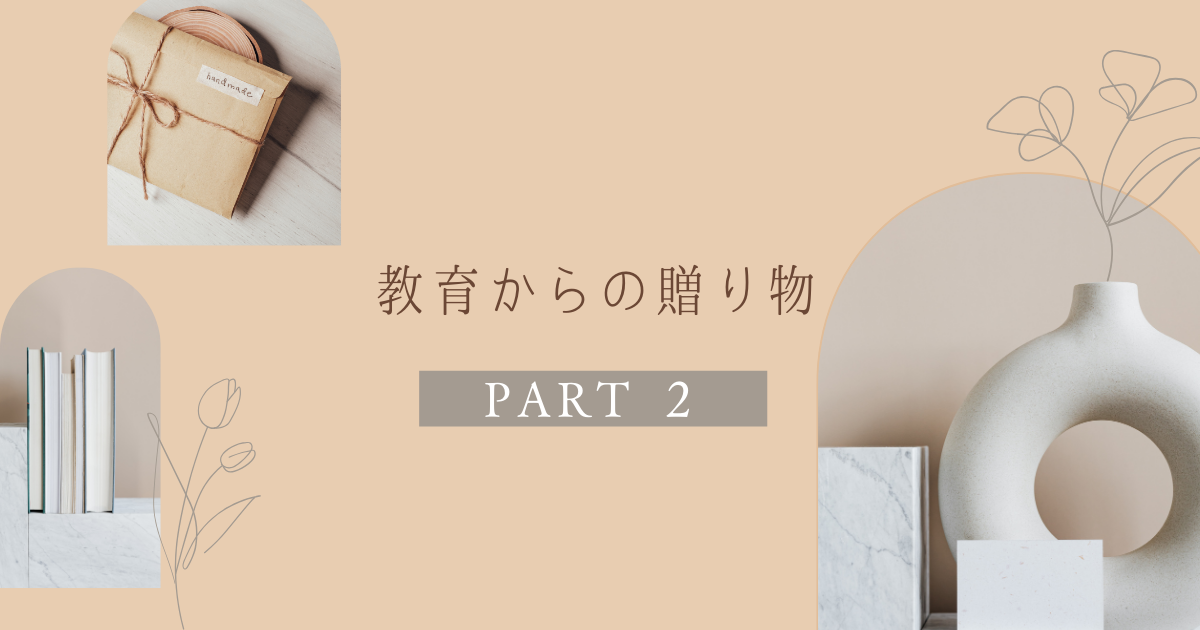



コメント