学びの場で生まれる「理解の差」
教育の現場では、必ず「理解の差」が生まれます。
同じことを学んでいても、人によって受け取り方や理解の深さは違います。
その差をどう埋めていくかは、教育をする立場にとって大きな課題です。
私が大切にしていること
私は、自分の考えをアウトプットすることが理解の差を埋める第一歩だと感じています。
たとえ間違っていたとしても、相手に伝え、修正してもらうことで理解が深まるからです。
30cmと50cmの差
例えば、自分の理解度を「30cm」と仮定し、相手が「50cm」だとします。
この20cmの差は、私が考えを口に出さなければ決して埋まりません。
しかし、自分の考えを相手に伝え、修正や補足を受けることで、同じ高さに近づいていけます。
実際のフォローで意識していること
教育対象者をフォローするときも、私は必ず「相手の理解の深さ」を確認するようにしています。
- 「患者さんの情報をどう捉えている?」
- 「今どんな治療をしている?」
こうした問いかけを通して、相手がどの地点まで理解しているのかを確認し、差を埋めるサポートをしています。
こちらが説明するだけではなく、相手の考えを引き出すことで、学びが一方通行にならず、対話によって定着していくのです。
実践していること
私は日頃から、医師や同僚にこうした確認をしています。
- 「患者さんの状況はこういうことですよね?」
- 「今の治療や薬はこういう意味ですか?」
こうしたやり取りは、単なる質問ではなく、自分の理解を相手に確かめてもらう作業です。
それによって、私自身の学びが定着し、確信に変わっていきます。
まとめ
理解の差を埋めるためには、勇気を持ってアウトプットすることが欠かせません。
間違えることを恐れずに、自分の考えを言葉にすること。
そして、相手の理解を確かめながら共に考えること。
その積み重ねが、教育の場での成長につながると私は信じています。
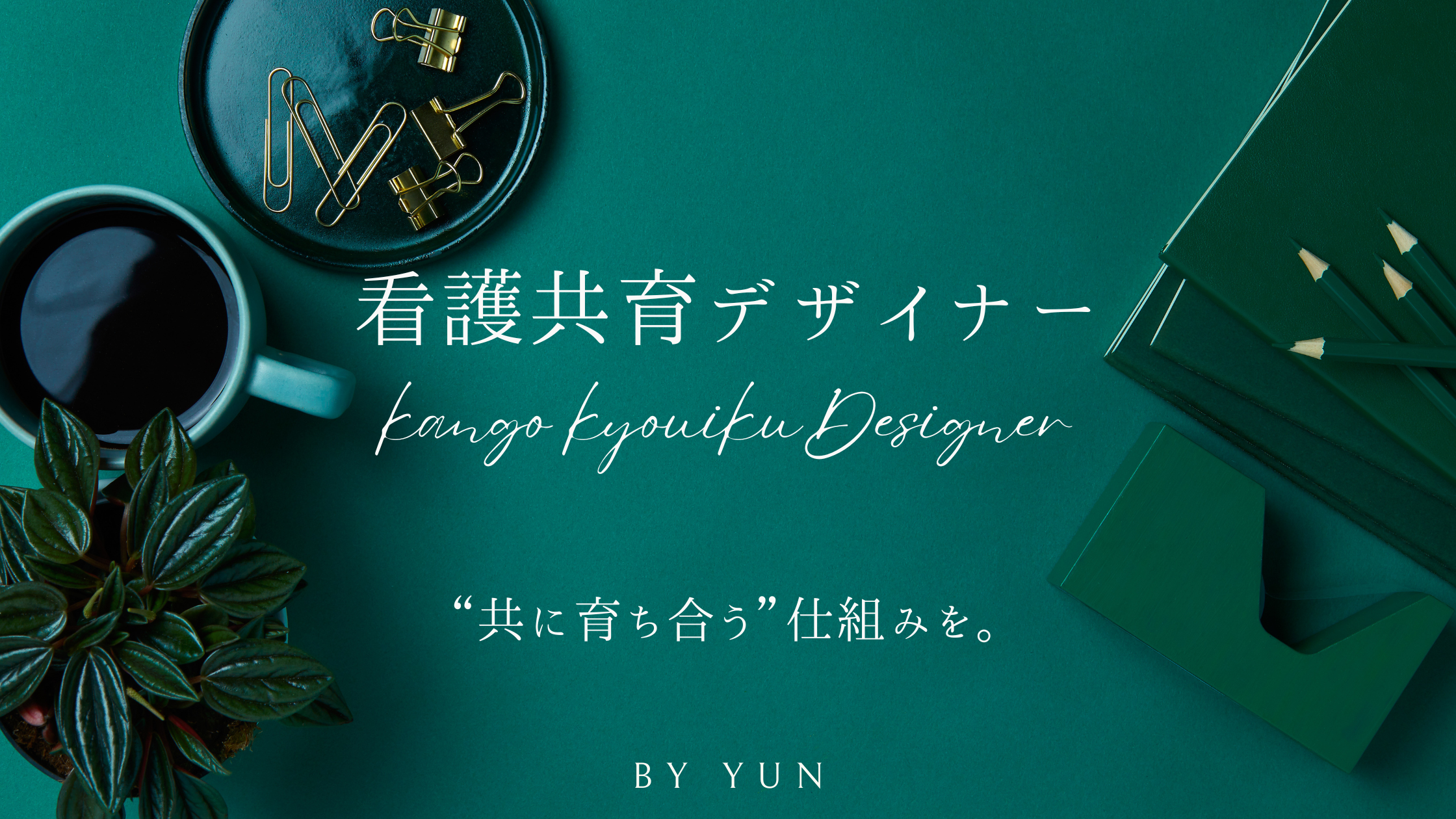
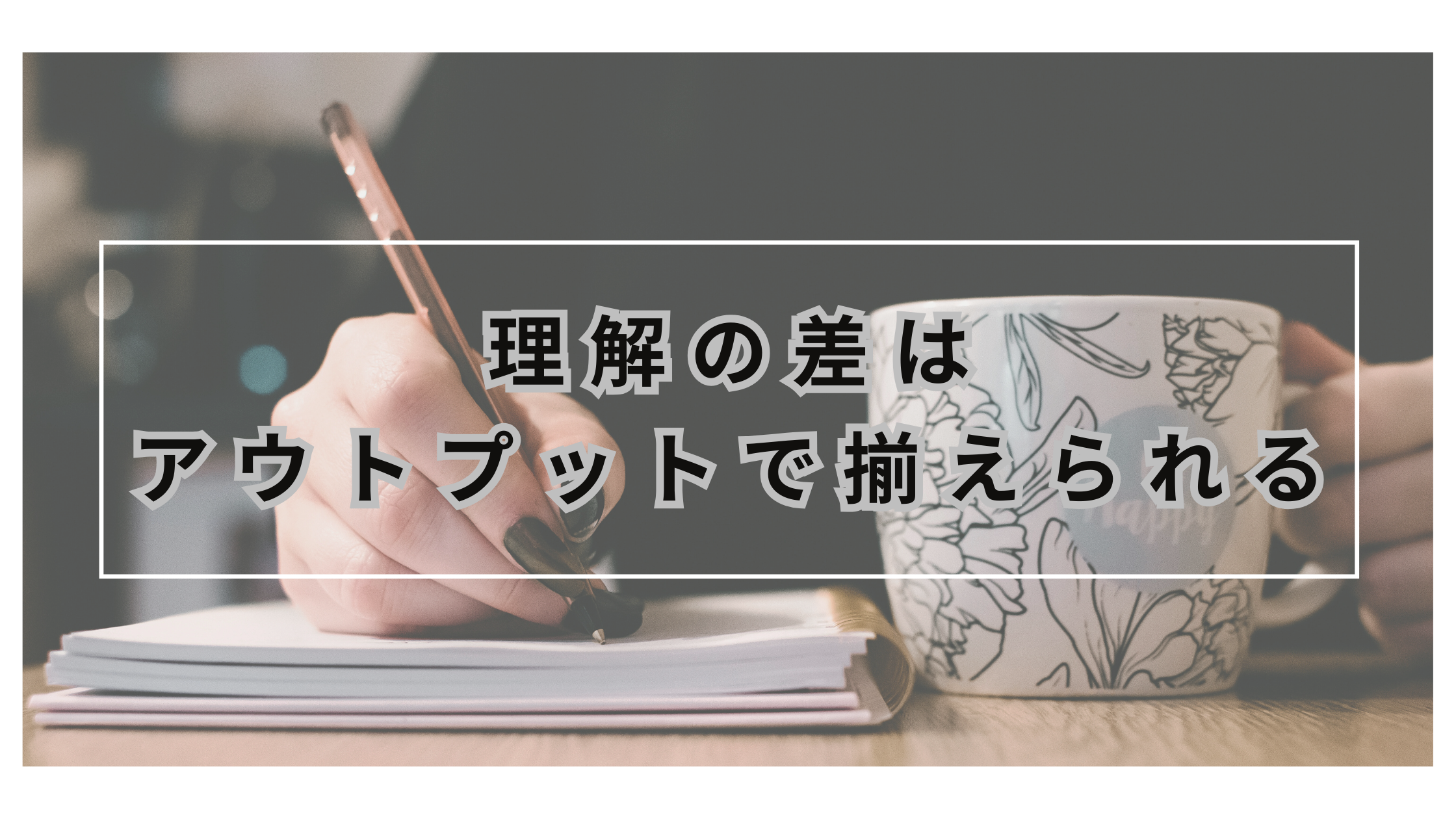

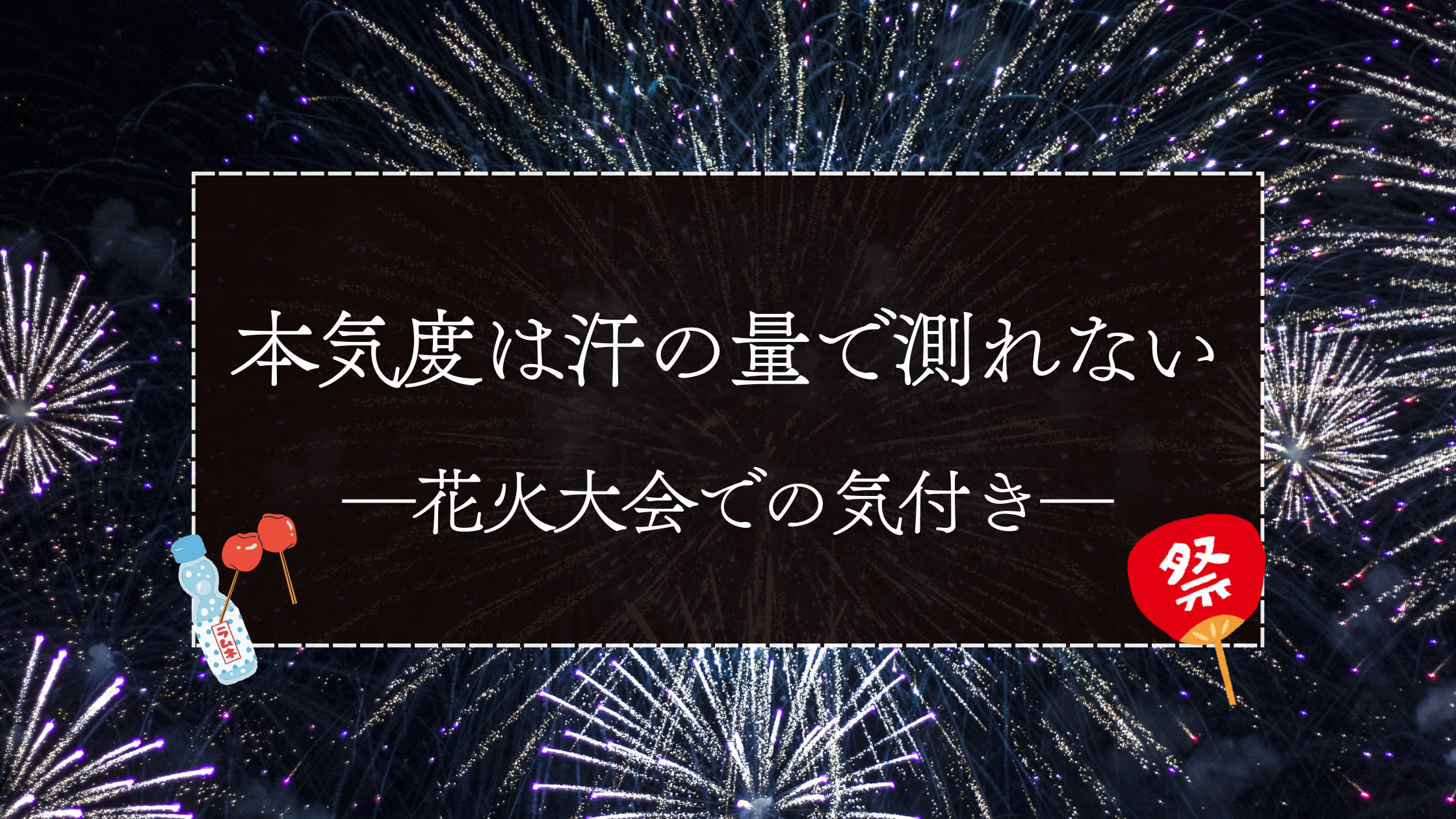
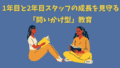
コメント