〜受け身から主体性を育てる関わり方〜
はじめに
重症患者の管理は、教育のチャンスでもあります。
昨日、当院で初めてのVAV-ECMO導入がありました。
私自身も初めての経験で学びながらでしたが、リーダーとして現場を見守りつつ、
スタッフへの教育も意識した一日でした。
「経験を自分ごととしてとらえること」
これが学びの深さを大きく変えると感じた夜勤でした。
初めてのVAV-ECMO導入
当院で初めてVAV-ECMOを導入する状況で、緊張感のある夜勤でした。
私はリーダーとしてこの患者さんを1人で受け持ち、
残りのメンバーで他の部屋を割り振り。
医師と管理方法をすり合わせ、申し送り時点で管理の把握はできました。
しかし、これは私にとっても大きな挑戦であり、学びの場でもありました。
学びに来ないスタッフたち…
メンバーは20代1名、30代2名。
そのうち1人はリーダー経験者ですが、ECMO管理は独り立ちできていません。
それでも、誰も自ら学びに来ないことに驚きました。
「自分ごとではない」という空気が漂っていて、
見慣れない機器に対する不安や怖さもあるのだと思います。
そんな中、携帯を触っているスタッフを見つけて、
「仕事中は触らないで」と注意。
現場の緊張感が薄れていることに、少し危機感を覚えました。
経験を“自分ごと”に変える声かけ
このままではいけないと感じ、まずは1人のスタッフに声をかけました。
「血ガス取ったことある?」「処置やったことある?」
「ないです」と答えたので、そのまま連れて行き、
血ガス採取や処置を一緒に経験させながら丁寧に説明しました。
さらに、こう声をかけました。
「次の日勤でこの患者さん受け持ってもらうからね。」
すると、そのスタッフは自分の持ち場に戻ってすぐに参考書を開き、
処置のときには自ら来て一緒に経験するようになりました。
この変化を見て、「学びを自分ごとにするきっかけ」の大切さを強く感じました。
主体性を育てるために意識したこと
① 怖さを前提に寄り添う
- 初めての機器や処置は怖いのが当たり前。
- だからこそ、「一緒にやるから大丈夫」という安心感を伝える。
② “受け身”から“自分ごと”への切り替え
- 「あなたが次に受け持つから」「準備してきてね」という声かけが効果的。
- 学ぶ理由を明確にすると、主体的な行動が引き出せます。
③ 小さな成功体験を積ませる
- 初めての処置を一緒にやる → 「できた」という感覚が次の学びにつながる。
- ECMOのような大きな症例こそ、一歩目のハードルを下げることが大事。
教育者として感じた課題
今回、あるスタッフは予習し、処置にも積極的に関わるようになりました。
一方で、リーダー経験者や20代スタッフはほとんど学びに来ず、
教育への温度差を強く感じました。
こうした「学ぶ人」と「学ばない人」の差を埋めるには、
個人任せではなく、チーム全体で学ぶ仕組みづくりが必要。
…だとは、正直思いますが、これは、綺麗事だなと思います。
いつもまで、もおんぶに抱っこ状態だと思ってもらったら困ります。
教育者として、一人の人として、私も教えたいスタッフとそうではないスタッフはいます。
それは、仕事の姿勢に現れています。一生懸命するか、ただこなして終わっているだけか。
これには本当に、教育したいという気持ちに差が生まれます。
本当はチーム全体での学ぶ仕組みは必要だとは思いますが、まずは個人から。
まとめ
- ECMO導入は、教育の大きなチャンス
- 「経験を自分ごとにする」ことで、学びの深さは大きく変わる
- 教える側の声かけ一つで、スタッフの主体性を引き出せる
- 今後はチーム全体で学ぶ仕組みづくりに挑戦していきたいが、まずは目の前の一人のスタッフから
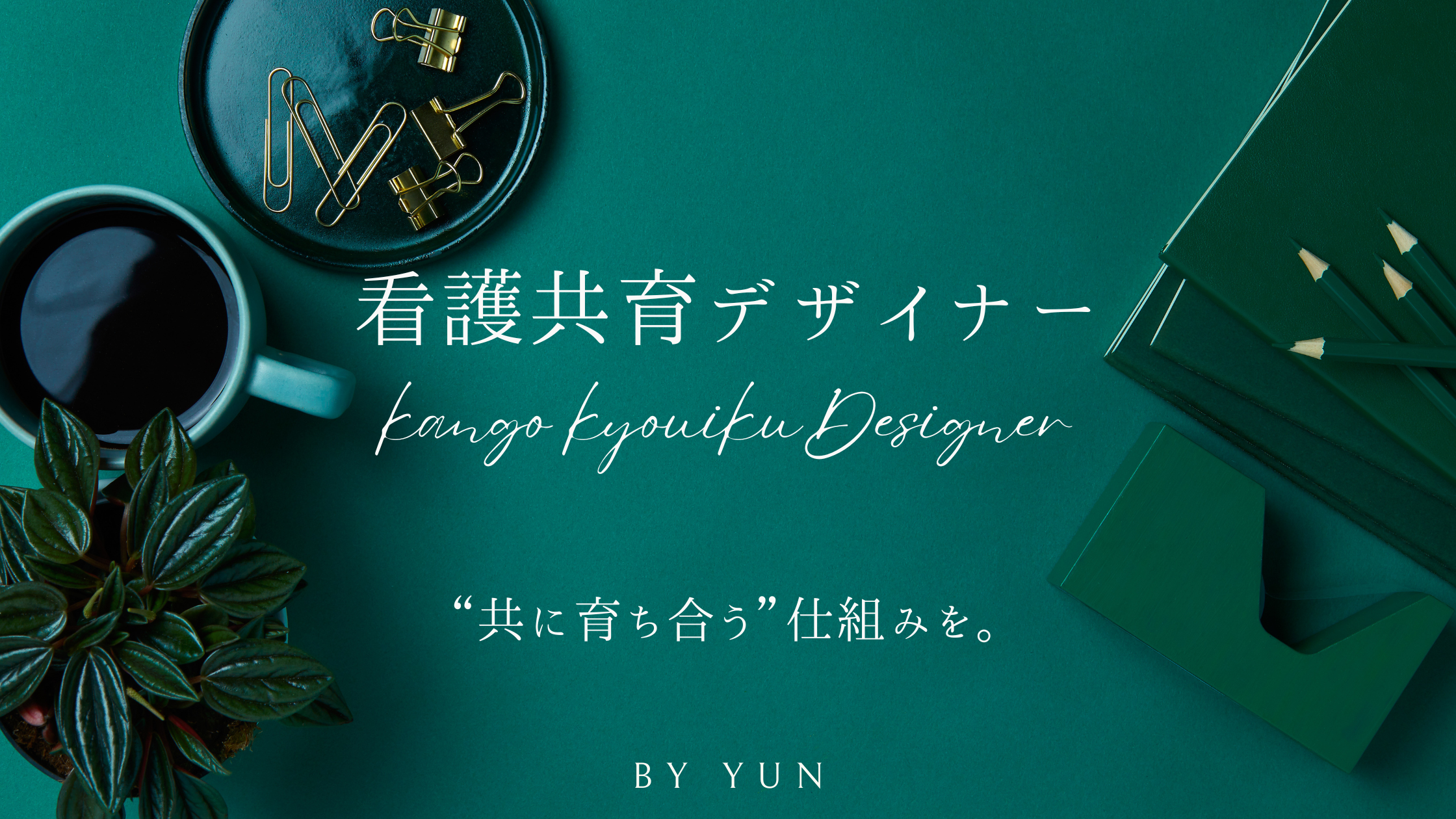
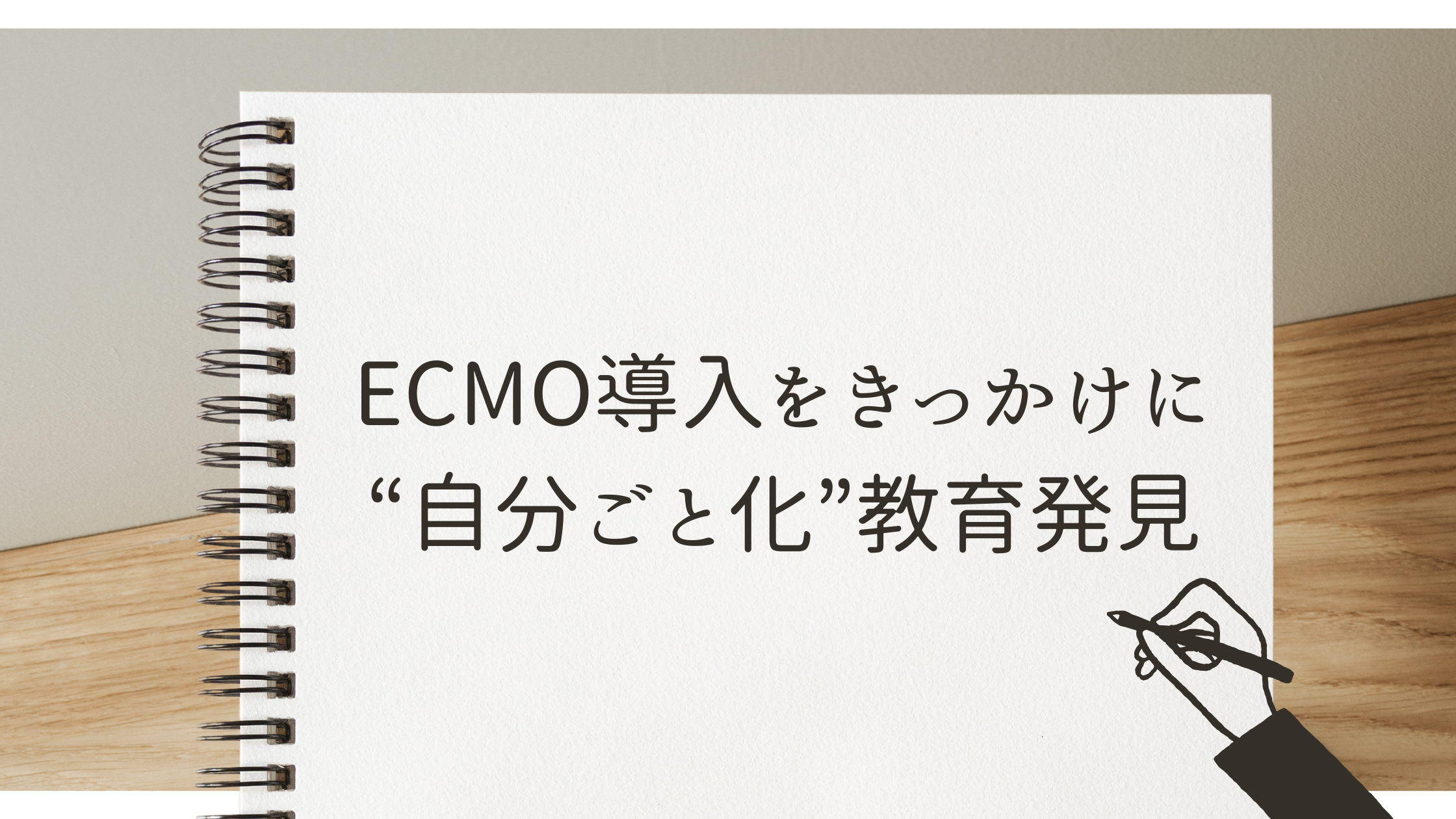

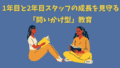
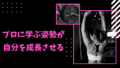
コメント